顧客以上に顧客を知り、提供価値を最大化するキーエンス。BtoB製造業はウェブサイトを使い倒して顧客を知るべし![後編]
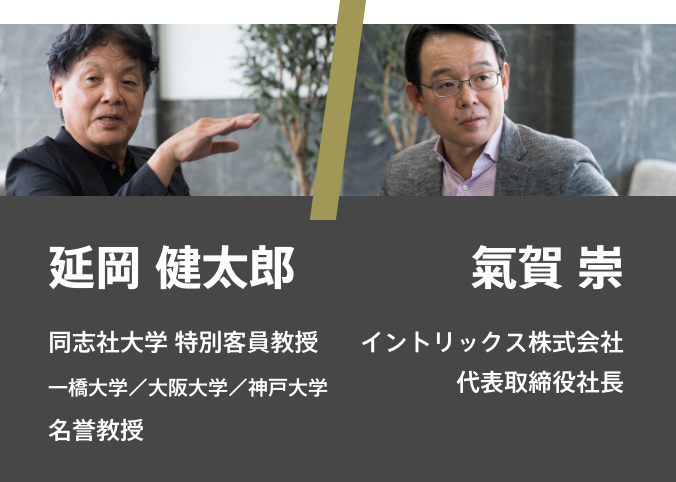
BtoB企業がキーエンスに近づくためのウェブ利用とは
氣賀:顧客の利益を考えることは全企業が目指すべきであり、その実現も「当たり前のことを愚直に追及する」しかありません。しかし、延岡先生がおっしゃるように、BtoB企業がキーエンスのようなやり方を一気に真似することは難しい。では、どうすればいいのか。大事なのは「顧客を知る」ことですから、その顧客と直接やりとりできるウェブサイトが、顧客視点を養うきっかけになりうると思っています。
延岡:ウェブサイトを中心とするデジタルマーケティングは手段であって、問題はどんな情報をどう置くかではないでしょうか。
氣賀:同感です。例えばプラントのオートメーション技術を展開している米エマソン・エレクトリックは、30年分のマニュアル・アーカイブをウェブサイトに置いています。そうすることで、マイナーすぎてすぐには入手できないと思っていた情報を、顧客は困った時にぱっと手に入れられる。これは1つの大きな価値です。
延岡:氣賀さんの著書で触れられている米農機メーカー、ジョン・ディアの部品ECも、顧客の利益を一生懸命上げようと機械のダウンタイムを減らそうとする試みです。顧客のオペレーションが止まることは、最悪なわけですから。
キーエンスが創業以来やっている受注商品の当日出荷も、工事のいらない流量センサもそれに当たります。多くの顧客は、自分たちのオペレーションがストップする時間を10分でも減らしたいと思っているのです。顧客にとっての困りごとは、顧客のコストを上げる要因になるので、解決につながる情報や機能のネットでの提供は、確かに意味のあることです。
氣賀:顧客10社の現場に出向くキーエンスのアプローチと比べると、受け身ではあります。ですが、ウェブサイトにどんな情報を置くかを考えることは、顧客の困りごとへの想像力が問われます。一足飛びにキーエンスになることは不可能ですが、顧客の利益を考えることはすべての企業が身につけなければならない。ウェブサイトを通じた顧客とのコミュニケーションは、顧客の利益を考える小さな第一歩となるのではないでしょうか。
延岡:その時に欠かせないのが、企業のウェブサイトの担当者も顧客のオペレーションを理解して、どういう情報を載せれば喜ぶかを考えることです。
例えば、普通1日かかる業務や修理が半日でできる商品を開発する場合、キーエンスはそれによって、大きな経済的価値が享受できる顧客がどれくらいいるかを調査します。同じ業務改善でも、コスト削減や売り上げ増加にどれほど結びつくのかは、顧客の使用方法や目的によって全く違うからです。しかも、十分に効果が出る30社の顧客の事例を持ってこないとその企画は通らないのです。業務や修理の時間を短くすることが、どれだけの価値を持つのか。そしてその価値は普遍的なのかをきっちり調べることが求められます。
氣賀:ジョン・ディアは、「おいしいとうもろこしのための土づくり」とか、「ハリケーンに負けないためには」という、自社の農機とは直接関係のない情報提供を100年以上続けています。顧客である農家がほしい情報とは何なのかを突き詰めた結果です。キーエンスも、ウェブサイトの中では自社商品の訴求を行なわずに、「静電気ドクター」とか、「流量知識.com」と言った基礎知識をテーマ別に載せていますね。

延岡:顧客に有益な情報として載せているのでしょう。
氣賀:そのようなことを調べようと思っても、生産現場に即した解説書は普通の本屋に置いてないわけですよ。だから、BtoB製造業の基礎知識はウェブサイトで調べる。すると、キーエンスのウェブサイトにたどり着く。学びの始めからキーエンスと接点ができて、そこで知識を得ることで、顧客は成長し利益を生み出すし、キーエンスの存在感も大きくなっていく。顧客に有益性を提供することを徹底的に考えたウェブサイトなのです。
延岡:ウェブサイトはあくまで手段ですが、氣賀さんのご指摘のように、顧客の利益を上げる情報提供に徹することができれば、大きな可能性が潜んでいるかもしれませんね。
氣賀:手段にすぎないということは、生かすも殺すも企業次第です。ただ、インターネットは顧客と直接コミュニケーションできるツールです。顧客の利益になることをしたいと考えている企業は、必ずこの特徴に注目しています。販売代理店や商社を挟むことが多いBtoB企業にとって、顧客と直接やりとりできる貴重なチャネルだからです。
延岡:だとすると、すでに顧客志向の強い企業がデジタルマーケティングをより活かすので、顧客志向の弱い企業との差はますます開くのではないですか。キーエンスは20年も前からコストダウンの事例を最重要コンテンツとして、ウェブサイトに掲載していました。
氣賀:するどいご指摘です。顧客志向の強いキーエンスは、ウェブサイトの使い方も非常にうまい。BtoB製造業のポータルを運営したり、データ分析を外販したり、今度はECも始めるなど、自身の事業領域とインターネットの特徴を見極めることにも優れている。「顧客の利益になるか」という視点が徹底しているため、その目的にかなうなら動きが柔軟で素早い。
一方、顧客志向の弱い企業は、商品のスペック中心で、顧客の利益に直結するような情報がなかったりするので、両者の差がかえって開いているのは事実です。
埋もれている日本企業の価値に光を当てるウェブサイト
延岡:問題は、顧客に価値を提供する視点を持たない大半の企業の方ですね。
氣賀:そうした企業は二種類に分かれます。引き合い依存が強く、顧客の要望に応えることでやってきた企業は、顧客の利益につながる提案力を持てるようになる道のりは険しいでしょう。
一方、実は顧客に価値を提供できる商品や提案力を持ちながらも、そのことを伝え切れていない企業もたくさんあると感じています。こうした企業は、伝え方の工夫によって、その埋もれた価値に光を当てることが可能です。
延岡:せっかくの顧客の利益につながる商品や提案力を、なぜ強く打ち出さないのでしょう。
氣賀:高度成長期はそうしたアピールをしなくても売れたし、控えめな日本人気質ということもあります。
例えば、機械メーカーをお手伝いしていると、設置工事が他社よりも楽だという訴求ポイントを聞くことがあります。本体形状や配管・ネジ穴の数の工夫などによって時間を短縮できる設計になっているのです。「設置の負荷が低い」ことは顧客の利益に直結する価値ですが、そうした打ち出しが目立たないことは珍しくありません。
訴求の内容が機能的価値であるスペック情報が中心で、設置の簡便さのような意味的価値をうまく言語化できていないのです。
延岡:日本企業のポテンシャルは、意味的なものも含めた顧客の価値をつくるところにあります。従来、日本企業の強みである優秀な技術者は、その辺のものごとが全部わかっていた。この機械メーカーの技術者は設置の仕方まで当然のように考えて、設計・開発まですべてをやった。それをやるのが、ひと昔前の日本の優秀な技術者です。
対してアメリカは分業制なので、技術の人は技術だけをやっている。分業がダメとは言いませんが、日本企業もこれを取り入れたことで、全体を見る力、顧客の利益を考える力は弱まりました。
氣賀:かたやキーエンスでは、入社3年に満たない社員が、顧客の工場を理解しているのですから、差は歴然ですね。
延岡:技術者や商品開発担当者も、そのメインの役割は顧客の価値を上げることであるとの自覚が必要です。そこをキーエンスは徹底していて、技術者とは呼ばずに商品開発担当者と呼びます。
他社の研修で、「うちも技術者にもっと顧客のところに行ってほしいけれど、なかなか行ってくれない。キーエンスはどうやって行かせているのですか?」と質問を受けるのですが、同社では技術者ではなく商品開発担当者なので、顧客の価値でしか評価されない。ですから、キーエンスの商品開発担当者は、自分の評価を上げるために、たとえ止められても顧客の所に足を運びます。その辺のことも根本的に変えないとダメということです。
いずれにしても、意味的価値のある商品や提案力がある場合は、きちんとそのことを伝えないともったいないですね。
氣賀:意味的価値を表現できていないケースは他にもあります。例えば建設機械、鉱山機械の世界だと、ボルボやキャタピラーのウェブサイトには長期間使った時の燃費やメンテナンス・修理費用など、トータルのライフタイムコストをシミュレーションする機能があるのですが、日本企業のウェブサイトにはありません。
延岡:日本企業はそこまでウェブサイトを利用していないのですね。ですが、そのレベルの競い合い、つまり機械本体の価格だけでなく、燃費や故障頻度、耐久性なども反映したライフタイムコストを比較したら、日本製の機械は勝てるのではありませんか?
氣賀:はい、ご指摘のように、多くの日本企業はメンテナンスやサービスの強みで、安価な中国製に対抗する方針です。つまり、ライフタイムコストでならば勝てると言っているわけです。でも、それを言語化していないのです。
延岡:それは残念ですね。
氣賀:すごくもったいないです。営業の現場ではそうしたシミュレーションも行っているのですが、より手前の検討プロセスであるウェブサイトでの欧米企業との差は如実です。今はウェブサイトを通じ、顧客自らできるだけ情報を集め、営業と会う前に一次検討を済ませる時代です。顧客には早い段階で、自社の商品を使うことがどれだけの利益になるかを見せておくことが重要なのです。

手段から入るもよし:ウェブサイトは顧客を知る上での優れたツール
延岡:要するに、ウェブサイトでの情報発信においても、顧客にこういう情報を提供できたら、これだけ顧客の利益が上がるということを考えねばならないわけです。逆に、ウェブサイトを通じて顧客からの様々なコメントが入ってくるとこんなに商品が良くなってどれだけ自社の利益も上がりますよ、ということも同様に意識しなければなりません。
氣賀:今おっしゃられた情報発信・情報取得という双方向のやりとりを実現できると、さらに拡がりのあるコミュニケーションとなります。米半導体メーカーのテキサス・インスツルメンツがやっているコミュニティは、良い参考事例です。
延岡:オンラインコミュニティということですね。
氣賀:はい、そうです。テキサス・インスツルメンツのウェブサイトでは、回路設計時のいろんな質問に対して、社員だけではなくユーザーも答える形を取っています。回答者が多いので、回答のスピード、数、質のすべてが良くなります。そのため、コミュニティユーザーのロイヤリティは非常に高く、サンプルチップの発注率は非コミュニティユーザーの6倍に達しています。
延岡:これはマスカスタマイゼーションの好例ですね。多数のユーザーを相手にしながら、数多くの個別の質問に答えることで、顧客企業の利益を最大化しています。この取り組みはすごい。そうそう一般の顧客に集まってもらうことはできませんから。
氣賀:このケースは、リアルでは難しい顧客価値の最大化であり、ネットの特性を上手に活用しています。
オンラインコミュニティにせよ、ライフタイムコストのシミュレーションにせよ、基礎知識コンテンツにせよ、最初は他社の真似でもいいと思います。その運用過程で、自ずと顧客のことを考えざる得なくなるはずです。ビジネスマナーも、挨拶や名刺交換など形式的なマナーから入りますが、実際の業務を通じて、その本質が「相手を敬う心」であることに気づいていきますから。
本来はキーエンスみたいなリアルな組織が顧客価値を追求し、全社に浸透する形がベストです。ただ、なかなかそこまではできません。ならば、ウェブサイトを通じた顧客との直接コミュニケーションを体験することで、顧客を利するものが何なのかを感じるきっかけになればと思うのです。
延岡:顧客の利益を上げることが企業の目的であり、他はそのための手段にすぎないことさえ忘れなければ、手段から入ることがあってもいいのですよ。
そもそも目的から逆算すれば、デジタルマーケティングが合う企業・事業と合わない企業・事業があるはずです。そこはきちんと区別して対応しなければなりませんね。
氣賀:デジタルコミュニケーションでできることはかなり幅広く、なんでもできてしまいます。そのため、自分たちに合う使い方を見定めないと、間違った使い方、間違った努力を続けてしまうことにもなりかねない。延岡先生がおっしゃるように、合う合わないの分別をつけることはとても大切です。
延岡:キーエンスのようなリアルビジネスのやり方は、簡単に真似できるものではありませんが、顧客の利益を考えろと言い続けることが自分の社会的な役割だと思っています。
現実解を提供する氣賀さんの立場からは、顧客理解に向けて一歩でも二歩でも前進できるよう、企業に寄り添い続けてほしいと思います。そして、デジタルマーケティングが顧客の理解につながることを証明する事例を、ぜひたくさん作ってください。
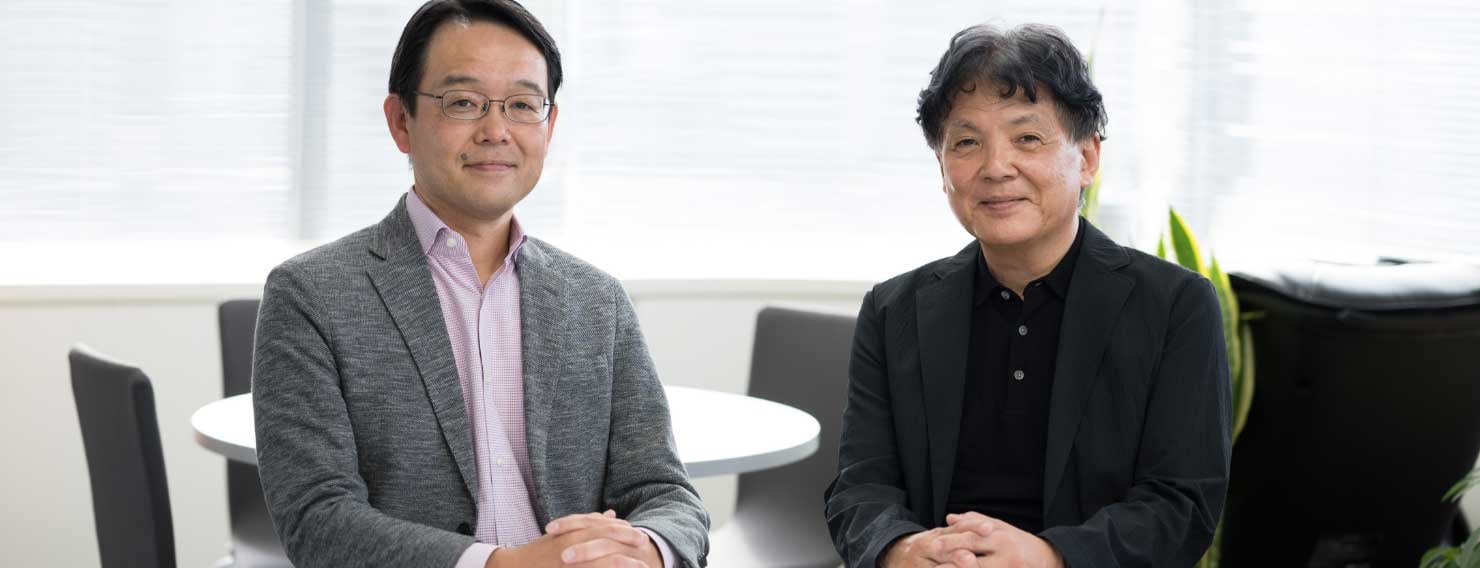
氣賀 崇 イントリックス株式会社 代表取締役社長
慶應義塾大学総合政策学部卒業後、米投資銀行にて、日本およびアジア株のアナリストを務める。海外インターネットビジネスへの投資に携わった後の2000年、サイエント株式会社に入社。デジタル戦略の策定やグローバルWebサイト群の築支援に従事。2009年、BtoB企業のデジタルコミュニケーションに特化したイントリックス株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。近著は『BtoB製造業のコミュニケーション革命』(東洋経済新報社)。
延岡 健太郎 同志社大学 特別客員教授
一橋大学/大阪大学/神戸大学 名誉教授
大阪大学工学部卒業。マツダ株式会社で商品戦略を担当後、マサチューセッツ工科大学(MIT)でPh.D(経営学博士)、MBA(経営学修士)取得。神戸大学経済経営研究所教授、一橋大学イノベーション研究センター長・教授、大阪大学経済学研究科教授を歴任。著書は『キーエンス 高付加価値経営の論理』のほか、『アート思考のものづくり』、『価値づくり経営の論理』、『MOT(技術経営)入門』(すべて日本経済新聞出版社)。
その他対談記事
驚異的な利益率を維持しながら成長を続けるキーエンス。製造業の理想形として長年ウォッチしてきた氣賀崇が、キーエンス研究の第一人者である延岡健太郎氏を招いての対談。前編は、日本のBtoB製造業がキーエンスから学べることは何かと問う氣賀に、延岡がキーエンスの成り立ちを解説し、プロ集団を作り上げることの難しさを語る。

BtoB製造業は日本の産業界の大谷翔平。もっとビッグマネーと名声を手にしていい。
日本の製造業は一流の技術力を持ち、成長し続けていると話すエコノミストの藻谷浩介氏。デジタルコミュニケーションを手掛ける氣賀崇はその指摘に深く頷き、足りないのは自身の価値の認識だと断言する。二人が語り合った、日本の製造業を取り巻く情報発信の現状と提言。

