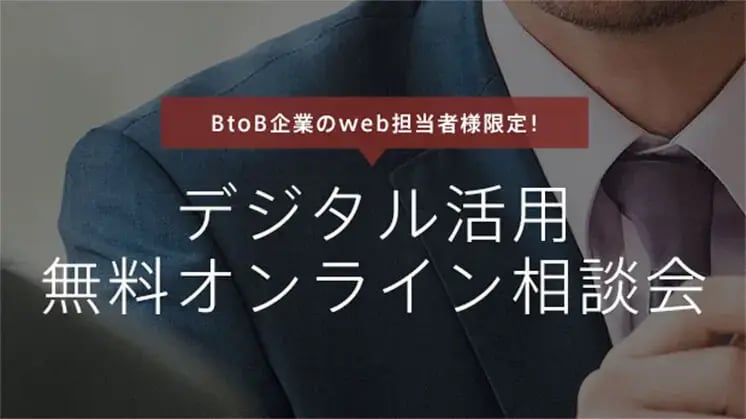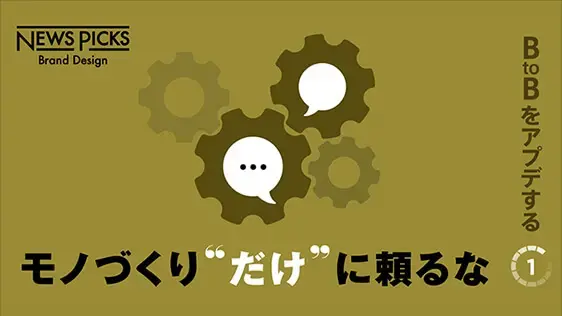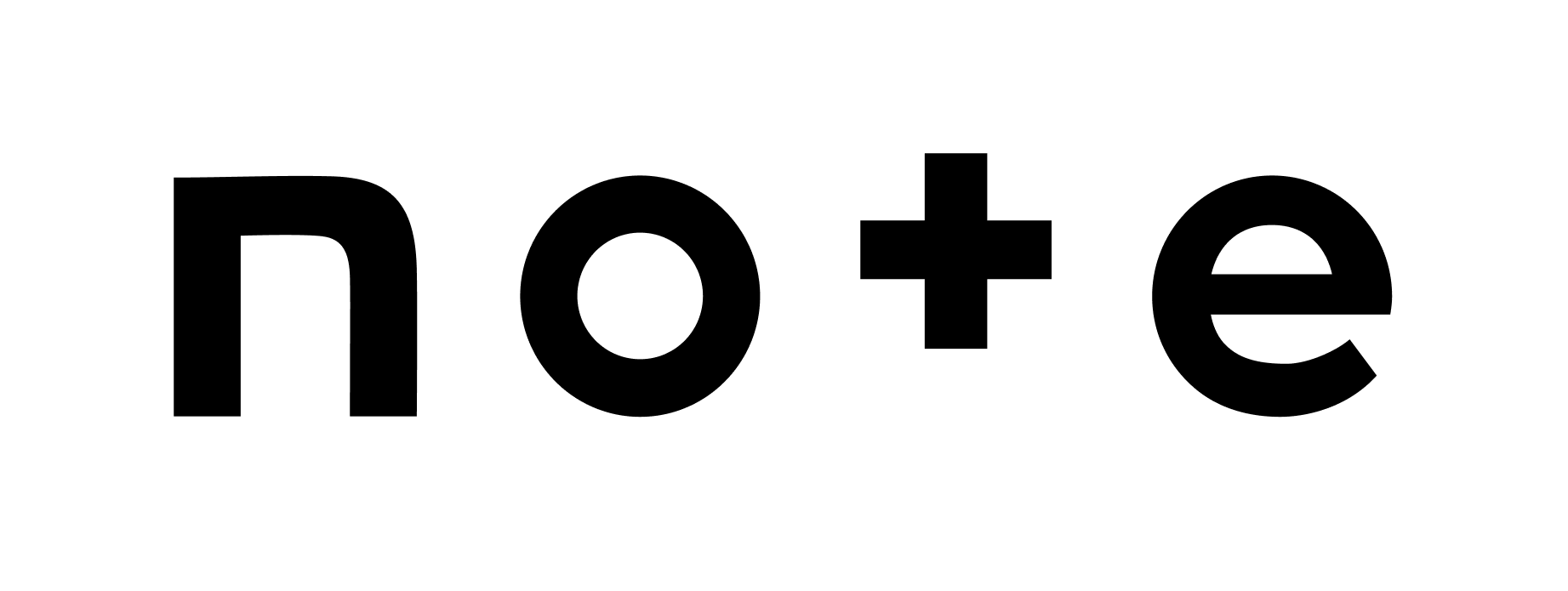マーケティング戦略が何も決まっていない場合は、最初に「どのような市場・ターゲットに新製品を売り込むか」を決めましょう。ターゲットの解像度を上げるためには「入社3年目の男性の営業担当者。他社の測定機を使っているが、検査担当者のスキルによって工数や品質にバラつきが生じていることに悩んでいる・週末はこのようなことをしている」といった具体的なペルソナを立てましょう。
そして競合他社の製品と比較した際の自社製品の強みを洗い出し、「このペルソナに魅力を伝えるにはどうしたら良いか」という視点でマーケティングを行う媒体を選定したり新製品のコピー、メリットの打ち出し方を考えていきましょう。
2.目的によってマーケティング施策を使い分ける
ペルソナが決定したら、次はどのようなマーケティング手法を取るかを決定します。Webでマーケティングを行う場合には、SNS広告・リスティング広告・SEOコンテンツ・広告枠への出稿などのさまざまな手法があります。新製品のマーケティングの目的は「認知拡大」なので手当たり次第にやってみる、ではお金をドブに捨てることになります。ペルソナをしっかり考えて何が最もターゲットの行動フェーズに合っていて最適なのかを考えましょう。
たとえば新製品の認知拡大が目的であれば、企業のSNSアカウントで新製品のプロモーション投稿を行ったり、有料のプレスリリースサイトを利用したりする方法も良いでしょう。フェーズが上がってニーズがある程度顕在化しているターゲットへのアプローチする場合は、能動的に検索している人に情報を出すリスティング広告やSEOコンテンツの配信、見込み顧客の育成はメルマガで定期的な情報配信をするなど手法はさまざまです。
マーケティング施策が決定したら、次は具体的に何をするのか決めましょう。まずは仮説ベースでカスタマージャーニーマップを作成し、ターゲットが製品を認知してから購入に至るまでの行動の流れを書き出します。その際に、それぞれのフェーズでターゲットに期待する行動変化もあわせて記載すると、よりやるべきことが見えてきます。
- 認知(課題を解決するための手段の一つとして、自社製品の存在に気づいてもらう)
- 理解(自社の製品でできること、他社製品にはない強みを知ってもらう)
- 検討(展示会でパンフレットや営業担当の名刺を入手/Webでホワイトペーパー入手。それをもとに製品購入を検討してもらう)
- 商談(上長または決裁者との商談をセッティングしてもらう)
- 納得(デモ機を導入してもらい、課題解決ができるという納得感を持ってもらう)
- 購入(実際に製品を購入し、社内で使用してもらう。不具合や懸念点があってもすぐに対応してもらえるという安心感を持ってもらう)
この流れが決定したら、それぞれのフェーズに対応するマーケティング施策を検討していきます。実際に始めたら最初の仮説に固執することなく何が最適か、本当に効果が出ているのかを常に検討しながらPDCAを回していく必要があります。
3.導入ハードルを下げるための施策を行っていることをアピールする
広告やさまざまなWebマーケティングで認知度をあげる一方で、「まずは見てもらう」「色々質問してもらう」「気軽に手に取ってもらって知ってもらう」という、導入ハードルを下げるための施策も重要です。BtoBの場合、新製品を導入する場合には社内の各部署・各担当者を説得する必要があるので、担当者もよほどの不具合や魅力がなければなるべく既存製品で済ませようと考えます。そのように新製品導入への壁が高いから、製品理解を深めてもらい少しでも導入へのハードルを下げるため、「とりあえず話を聞いてみよう」「試してみよう」といった気持ちにまで誘導することが重要です。ハードルを下げるためには、展示会やウェビナーなどを積極的に開催しましょう。
しかし、お金を出して準備をして展示会に出展したりウェビナーを開催しても、そのようなイベントがあること自体をターゲットに知ってもらわなければ集客にはつながりません。ペルソナの行動フェーズにより顧客の課題や悩みは異なるため、フェーズごとに「その悩みを解決できますよ」というフェーズごとの発信を行い関心を掴むことが大切です。まだ認知されているかどうかの段階では、「無料」「いつでも退室可能」など心理的な参加ハードルを下げることも大切です。
4. 他職種と連携してマーケティングを行う
具体的にマーケティングを施策の企画・実行し改善を進める際には、その新商品に関わった社内の他部署を巻き込むことも重要です。新製品の強みを洗い出す際には、開発担当者にこだわったポイントや苦労した点などを取材することで新製品のブランディングに活かすことが可能になります。また、他社製品の分析や顧客となりうるターゲットが抱える課題などは製品開発の段階である程度整理されている場合が多いため、そこを踏まえて市場を設定したりターゲットを絞ることで、マーケティング活動が効率化できます。
また、商談後の成約状況を営業担当に確認することで、ホワイトペーパーや展示会で収集した顧客情報から、マーケティングを強化すべきペルソナ像が可視化されたりより具体的に顧客像が見えてきます。さらに、展示会や商談で直接得たターゲットの課題を営業担当者から共有してもらうことで、ターゲット層の見直しやマーケティング施策の軌道修正などを行うことも可能になります。
商品開発時に利用したマーケティング情報を活用したり、資料請求や問い合わせなどで得たリアルな声をマーケティングに反映させることで、より精度の高いマーケティング活動が可能になります。製品開発や顧客とのやり取りに直接関わっていないマーケティング担当者のみで施策を考え流ことによって「絵に描いた餅」になってしまうケースは多々見られます。常に他部署と連携したり場合によっては部署異動を行うなどして、リアルな市場の声や新商品開発時のKPIを振り返りながら、より良いマーケティング施策をアップデートしていくことが重要です。
5. 成果が出るまで1年以上かかることを理解する
最後に重要なのは、「新商品の認知拡大には時間がかかる」という意識を持つことです。BtoBの製品は、ターゲットが製品を認知してから購入するまでに平均で半年~1年の期間を要すると言われています。ましてやまだ販売実績がなく市場やペルソナを探りながらマーケティング活動をしている状態で、すぐにターゲットに完全に合致したメッセージが届く可能性はかなり低いでしょう。
BtoBはBtoCに比べてターゲットの母数が少ない上にトライアンドエラーを繰り返しながら成功ルートを模索しなければなりません。新製品のマーケティングにおいては、検討の土台に上がること、そして実際に検討する期間も含めると決定まで1年以上になることも考慮に入れる必要があります。すぐに成果を出そうと焦って施策をコロコロ変えたりターゲットが違うのでは?と媒体を変えたりしていては、結果には繋がりません。最初の1年間は、決定したターゲット層やターゲットの抱えている課題を分析することに集中し、焦ってPDCAを回そうとしすぎないことも大切です。