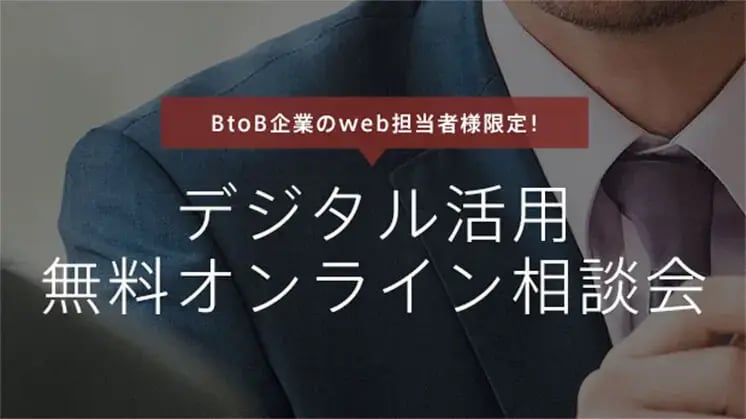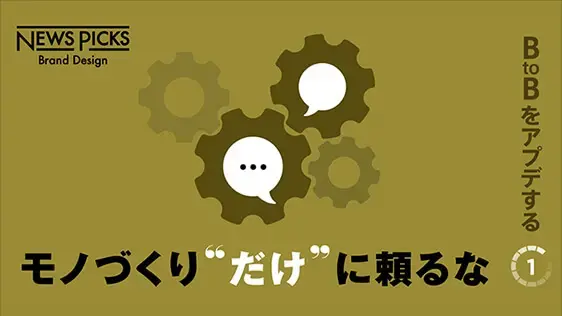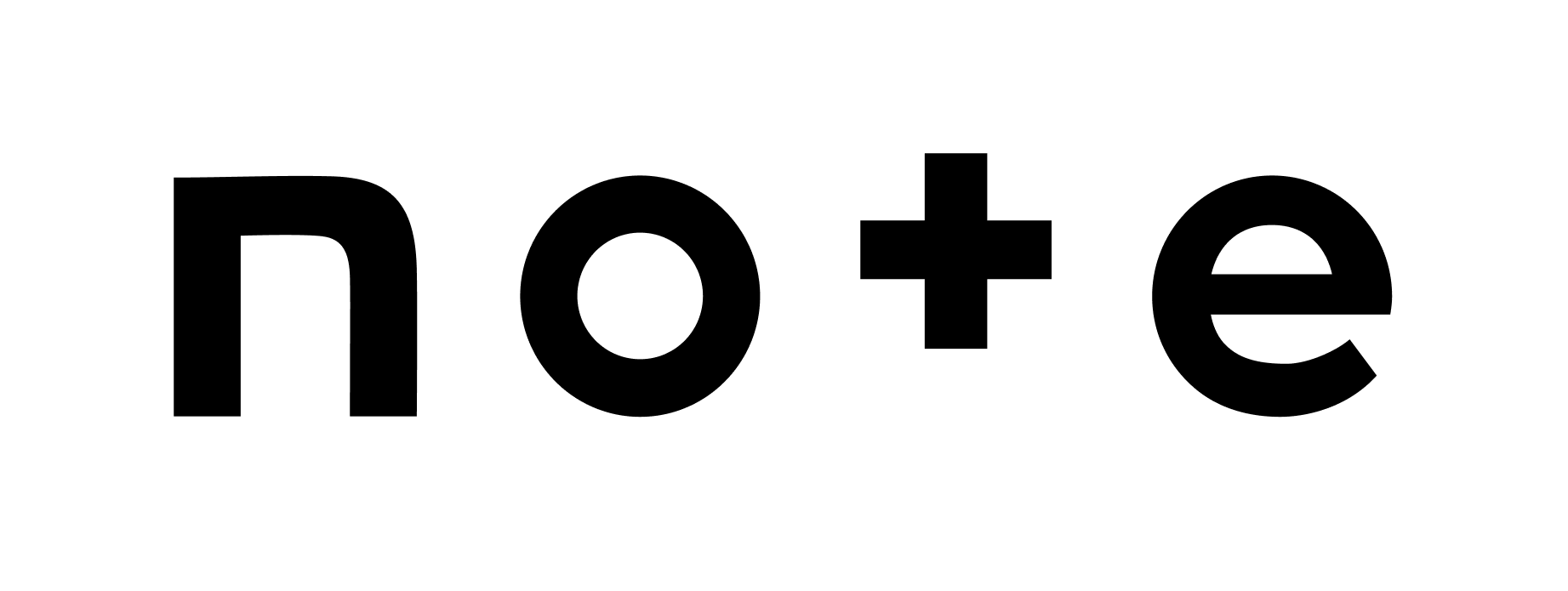データ分析の手法9選
課題解決の糸口となったり、経験則に依らない発想を可能にしたりするデータ分析。分析方法はもちろんひとつだけではなく、さまざまな手法があります。
主な方法を9つご紹介します。
バスケット分析
バスケット分析は買い物かごのなかにある商品を分析対象として、組み合わせの傾向などを分析します。有名な組み合わせとしては「おむつとビール」があります。
この組み合わせからは、子育てをしているかつビールを飲む顧客像が浮かびます。さらに年齢層やライフスタイルの推測も可能です。それらに基づいて新商品や他の組み合わせのアイデアを得られることがバスケット分析の特徴です。
ABC分析
ABC分析は、商品管理をする際にどの商品を重点的に管理するかを考える際に使われます。全体の売上高に占める商品(もしくは商品グループ)ごとの構成比率をA・B・Cの3種類にランク分けします。
商品の売上金額が大きい順に並べ、累計の構成比率が70%以下までの商品をA、71%〜90%までをB、91%〜100%までをCとして、売上全体に対する貢献度を視覚化する手法です。
クロス集計分析
アンケート調査によく用いられる手法です。例えば、データ分析への取り組みに関する調査をしたとします。縦軸に企業規模や業界、横軸に回答の内容(取り組み度合い)を配置して掛け合わせる(クロスする)と、企業規模や業界を切り口としたデータ分析への取り組み度合いを比較できます。
クロス集計は上記のように、調査に回答した企業や個人の属性によって傾向に違いがあるかどうかを分析する手法です。
因子分析
異なる複数のデータ間に存在する共通の因子を発見するための分析です。わかりやすい例としては、学校のテストにおける文系・理系の能力が挙げられます。
テストの成績を分析し、国語の成績が良い人は英語の成績も良い、数学の成績が良い人は理科の成績も良いといったデータが得られたとします。このとき国語・英語、数学・理科には共通する因子があると考えて、成績向上のために共通因子をいかに磨くかを考えていくのです。
アソシエーション分析
アソシエーション分析は、一見すると関連が見いだせないような多くのデータから相関関係を発見していく分析手法です。買い物かごを分析し、よく買われる商品の組み合わせを発見するバスケット分析はアソシエーション分析のひとつです。
インターネットショッピングサイトのレコメンド機能はアソシエーション分析の成果を活かしています。
決定木分析
「目的変数」と呼ばれる結果(結論)に至る要因を構成する要素を分析する手法です。構成要素は「説明変数」と呼ばれます。目的変数はどのような説明変数によって構成されているのか、分析結果を図解するとツリー状になることから「決定木」分析と呼ばれます。
例えば自社の提供している商品・サービスの利用者のうち「満足度が高い人」を目的変数とした場合、利用者の属性(年齢や所属企業、ライフスタイル等)などが説明変数となります。
クラスター分析
分析対象とするデータ群をグルーピングする分析手法で、クラスターは「集団」を意味します。ビジネスにおいては、顧客を属性ごとにグルーピングしたり、自社が参加している市場や自社の企業としての特徴を俯瞰する際に役立ちます。
グルーピングする際の基準や、分析手法もさまざまあるため、目的に応じて適した手法を選択することが大切です。
主成分分析
主成分分析は、複数の要因が絡み合っている事象について、その構成要素をなるべくシンプルに把握したいときに用いられます。「売上」のような定量的なものよりは、「満足度」のような定性的なデータを分析する際に用いられます。
顧客満足度はどのような成分によって構成されるのか、商品やサービスの「質」は何によって決まるのか、といった問いに強い分析手法です。
回帰分析
回帰分析は決定木分析と似ているもので、とある結果に対してどのような変数が影響を及ぼしているのかを分析する手法です。決定木分析はYesまたはNoで分岐されたツリーが作成されますが、回帰分析では最終的には回帰式という計算式が作成されます。
広告キャンペーンの成果を計測したり、モデル式を作って値を代入し、施策の成果を予測したりする用い方があります。