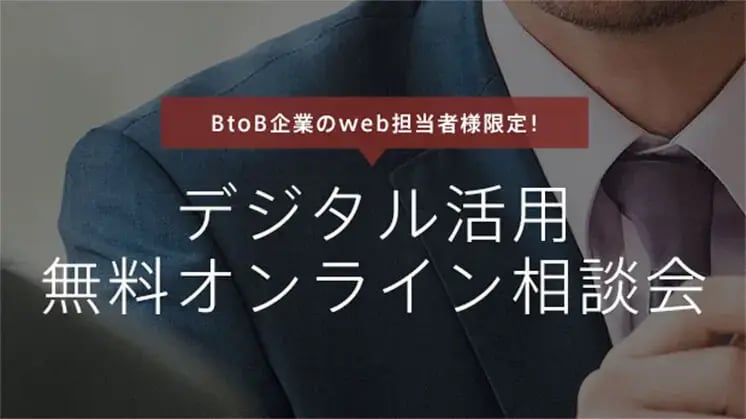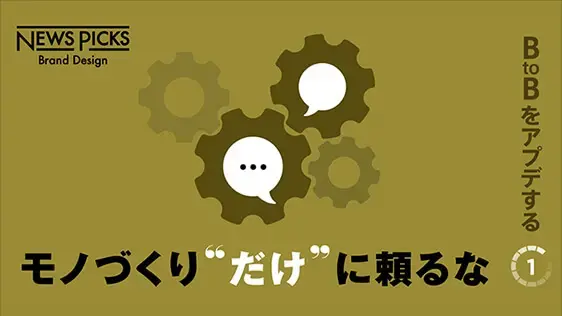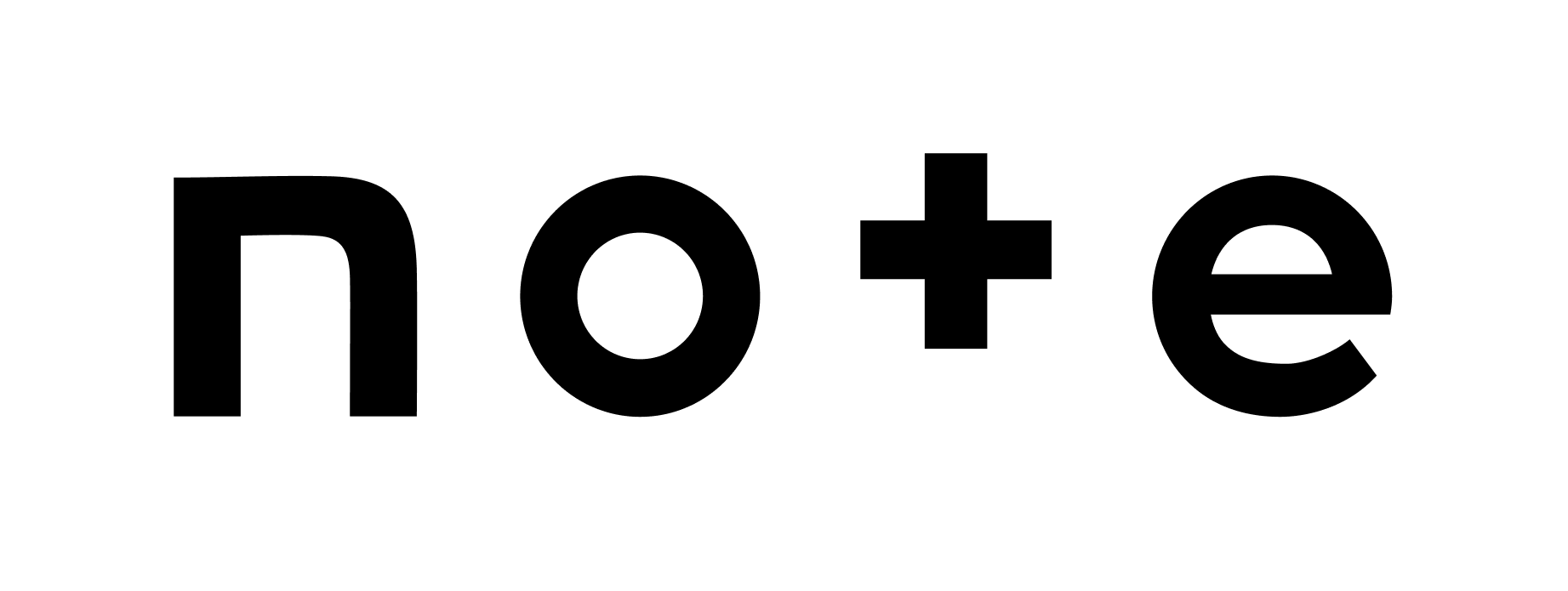DXロードマップ作成に必要な4つの手順
DXロードマップを作成するには4つのSTEPが必要です。1つ目は全社・全部門で共有ができるDX ビジョンの策定。多くの部署がまたがるDX化だからこそ社内の誰もが共感できるDX ビジョンが重要になります。
2つ目はビジョンの実現のために必要な現状分析と強みの洗い出しです。3つ目は実現可能なKPIの設定、そして最後がこれら全てをまとめたロードマップ(スケジューリング)の作成です。
順を追って手順や気をつけるべき点を解説します。
STEP1)DXロードマップのビジョンの作成
ロードマップを作成する際にまず必要なのが、社内で『DX化で目指すべきビジョン』を決定することです。
企業におけるビジョンとは『企業が目指す理想的な姿』であり、DXロードマップ作成の際のビジョンとは、『DXを推進することによってどのような企業になりたいか』を言語化したものです。
会社のDX化を成功させるためには他部門での連携が必須で、各部署にそれぞれの役割が発生します。今まではあまり接点がなかった他部署間でのやり取りが頻繁に発生するからこそ、社内で共有できるビジョンが重要なのです。
またDX化のビジョンは、各部署・各担当者が壁にぶち当たったり目的が見えなくなった際に、何度でも立ち返る羅針盤ともなります。DX化は経営者を筆頭にして組織全体で変革に取り組む必要があるので、経営者の理想像を現実可能なレベルで盛り込みつつ作成者が特定の部門に偏ることのないよう留意し、企業理念や強みに基づいて策定しましょう。
STEP2)DXロードマップ作成のための現状分析
ビジョンの策定が終わったら、具体的なロードマップの作成に取り掛かります。ロードマップの作成の際には、競合のリサーチや業界の市場の動向なども鑑み、それらを元に自社の強みの把握や現状分析を行います。
現状分析を行うことで、自社が強みとして今後も伸ばすべき点・あるいは改善すべき点が見えてきます。そもそもDX化する目的は国内外問わず競争力を高め強い企業になること。自社の強みに付加価値をつけられる目標設定をすることが重要となります。
またしっかりとした現状分析を行なってからDXロードマップを作成することで、目標と現実の大きな乖離を防げます。現状からかけ離れた大きすぎる目標を設定しても、社員のモチベーションの低下や過重労働などを招き、結果的には失敗に終わるケースがほとんどです。
現状分析を行う際には、社内調査や担当者からヒアリングすると共に、一般的なフレームワーク(3C分析・ 4C分析・SWOT分析・PEST分析・VC分析など)も有効です。
STEP3)DXロードマップのKPI設定
KPIの目標設定は、これが実現できているのかどうかを誰もが評価しやすいことに加え、全社員・担当者・経営者が適正だと納得できる内容や数値にする必要があります。さらに、明確性・測定可能性・達成可能性などの視点から、以下に留意し設定することが求められます。
- そのKPIの数値が改善されれば、売り上げやコスト削減などに具体的な改善が見られるか
- そのKPIは各部門の作業内容も含め実現可能か
- そのKPIはPDCAの回し方を具体的にイメージでき、また無理が生じた場合に修正可能か
計画当初設定したKPIが、トラブルや新たに発見された課題などによって進捗が遅れたり、実現不可能であることが判明する場合も少なくありません。そのような際には速やかにKPIを見直す柔軟性も必要です。
参考までに、埼玉県庁のDX化のKPIは部署ごとに「行政手続きのオンライン率」「介護施設の介護ロボット導入率」「行政利用率のオンライン率向上」のように定めています。
STEP4)DXロードマップのKPI設定
STEP1から3までが揃ったら、「何をどの順番で・どんなスケジュールで行うか」を年表のように図式化していきます。これが完成したものがDXロードマップとなります。
まずは最終的なKPIを決定した後、各年度ごとにやるべきことやフェーズなどを大まかに作成。年度の枠が決まったあとは、実現可能なスケジュールで四半期ごと・月ごとなどに落とし込んでいきます。
年度のゴールはしっかり決めるものの、数ヶ月単位などの小さな期間のスケジュールは定期的に見直しをしながら現実に即して進めていきましょう。
このような全体のKPIの他に、短期間のマイルストーンも設定します。これは実現可能な内容である必要があり、1週間・1ヶ月などの短期で具体的に設定をし、社員のモチベーション低下を防ぎます。
目の前の小さなマイルストーンをコツコツと積み重ねていった結果、数年後に本来のKPIが達成されているというのが理想的なスケジューリングです。