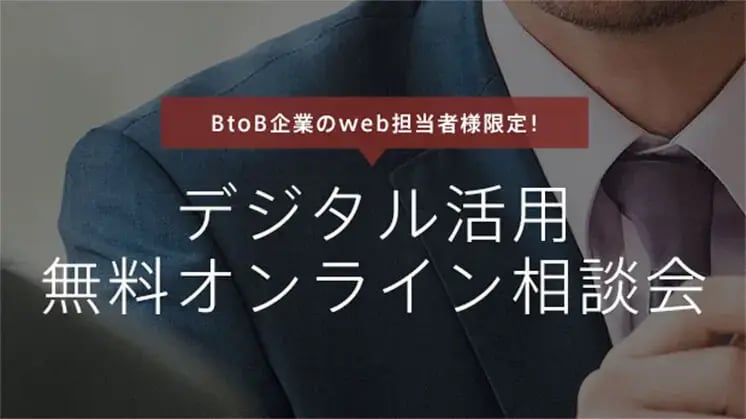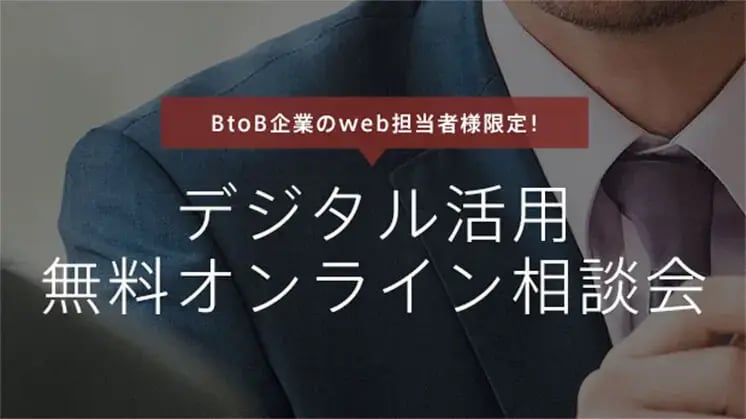経済産業省が育成するDX人材
DX人材の採用が難しい場合、どのようにして育成したらよいのでしょうか。企業のDXを進めるには、必要な知識・スキルを学びながら実践を積んでいくほかありません。しかし必要な人材像や、知識・スキルをどのようにして身につけていけばよいのか、ヒントすら無いという状況の方もいらっしゃると思います。
以下に、育成の進め方DX人材育成に関するキーワードや経済産業省の提供する育成支援プラットフォーム、支援策をご紹介します。
DX人材の育成に欠かせない「リスキリング」
リクルートワークス研究所の作成した資料によると、リスキリングとは以下のように説明されています。
—
「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、 必要なスキルを獲得する/させること
—
大人になってから自分の興味関心のある分野を勉強し直す「学び直し」とは少し異なり、仕事において何らかの価値を発揮するために学ぶことが特徴です。
米アマゾンは自社の従業員10万人をリスキリングすると発表、国内企業では日立製作所が2020年に国内グループ企業の全従業員16万人にDX基礎教育を実施しました。企業が市場に提供する価値を生むプロセスそのものを変化させるには、特定の従業員のスキルアップだけでは限界があることが伺えます。
また2030年にはIT人材が最大で79万人不足するという試算もあり、経済産業省はリスキル講座の認定制度を設けました。給付制度や助成金との連携を図ることで費用を支援できる仕組みを構築するなど、後方支援の動きも活発になっています。
※参考:
リスキリングとは ーDX時代の人材戦略と世界の潮流ー
経済産業省主催「リスキル講座認定制度説明会」
第四次産業革命スキル習得講座認定制度
平成 30 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備(IT 人材等育成支援のための調査分析事業)- IT 人材需給に関する調査 -
デジタル人材育成プラットフォーム ポータルサイト「マナビDX(デラックス)」
経済産業省は認定制度のほか、情報処理推進機構(IPA)と連携し「デジタル人材育成プラットフォーム「マナビDX」」を開設しています。
デジタルに関する知識・能力の習得を、必要とする全ての人に提供するためのポータルサイトで、初心者〜専門スキルを身につけたい方、研修として活用したい企業の方など幅広い方を対象とするものです。
基礎的なものから実践的なものまで、有償・無償の講座情報がまとめられています。トップページから「マナビDXで何ができるの?」のページに遷移すると、想定利用者ごとにおすすめの講座一覧を閲覧できます。
企業のDX推進を促進するために2022年の3月29日に開設された新しいプラットフォームです。
※参考:
いま学びたい、お役立ちコンテンツ(DX・デジタル技術・ビジネス変革、等)
DXリテラシー標準
経済産業省の設けたDX人材の目安に「DXリテラシー標準」があります。ここには全ての社会人が身につけるべきデジタルスキルが示されており、DXを推進するためにそれぞれが何をできるのかを考えられるようになることを目指しています。
例えば経営層の方であれば、DXを進めるための経営計画の策定が、製造・開発部門の方であれば自社の現場にどのような技術を応用できそうかの想定ができるようになることが理想です。
現場でDXを推進していくにあたって、知っておくべき技術知識、技術の活用方法に関する知識がまとめられたものであり、実際に推進していくには経営計画を立てる能力やマネジメント能力が求められることに注意が必要です。
DXリテラシー標準は、Why・What・Howの3つに大別されており、なぜDXが重要なのか、何を学べばよいのか、どのように応用可能なのかの指針を確認できるようになっています。
働き手の一人ひとりがDXを自分ごとと捉えて自ら変革に向けて動きだせるようになることが狙いです。
※参考:
DXリテラシー標準
デジタル人材育成協議会
2022年9月、文部科学省と経済産業省主導のもと「デジタル人材育成協議会」が開催されました。
地域の社会課題をデジタル技術によって解決するには、首都だけでなく全国各地にその担い手が必要です。また広域にわたる人材育成には産学官の連携も必須です。そこで、政府・地方公共団体・産業界・大学・高等専門学校を構成員とした意見交換が行われました。
大学・高等専門学校では、新社会人になった際に必要なデジタルリテラシーを確実に身につけられる教育の提供を推進。現役社会人の方たちにはあらたにDXリテラシー標準を示し、最終的にはDXの推進を担う全ての社会人が推進のためのリテラシーを獲得することを趣旨としています。
文部科学省は大学・高等専門学校にむけた「数理・データサイエンス・AI教育」の全国展開を推進、経済産業省ではスキル標準の提示や、「マナビDX(デラックス)」のような育成プラットフォームの提供を進めています。
育成の方向性は地域ニーズによって異なり、例えば九州では半導体人材の育成・確保が重視されているようです。日本の各地域ごとに産学連携で人材育成を進めていきます。
※参考:
デジタル人材の育成体制