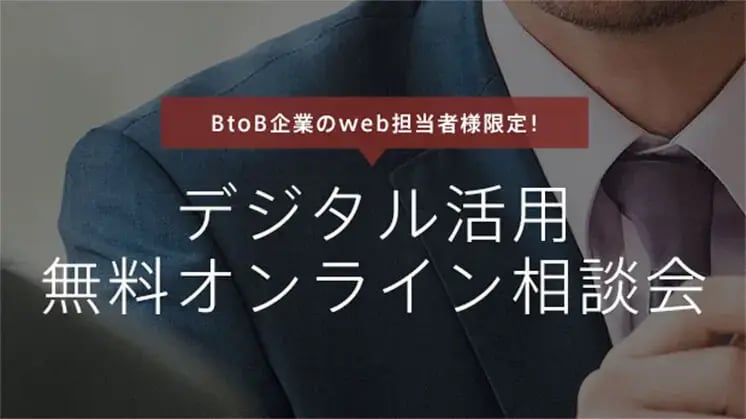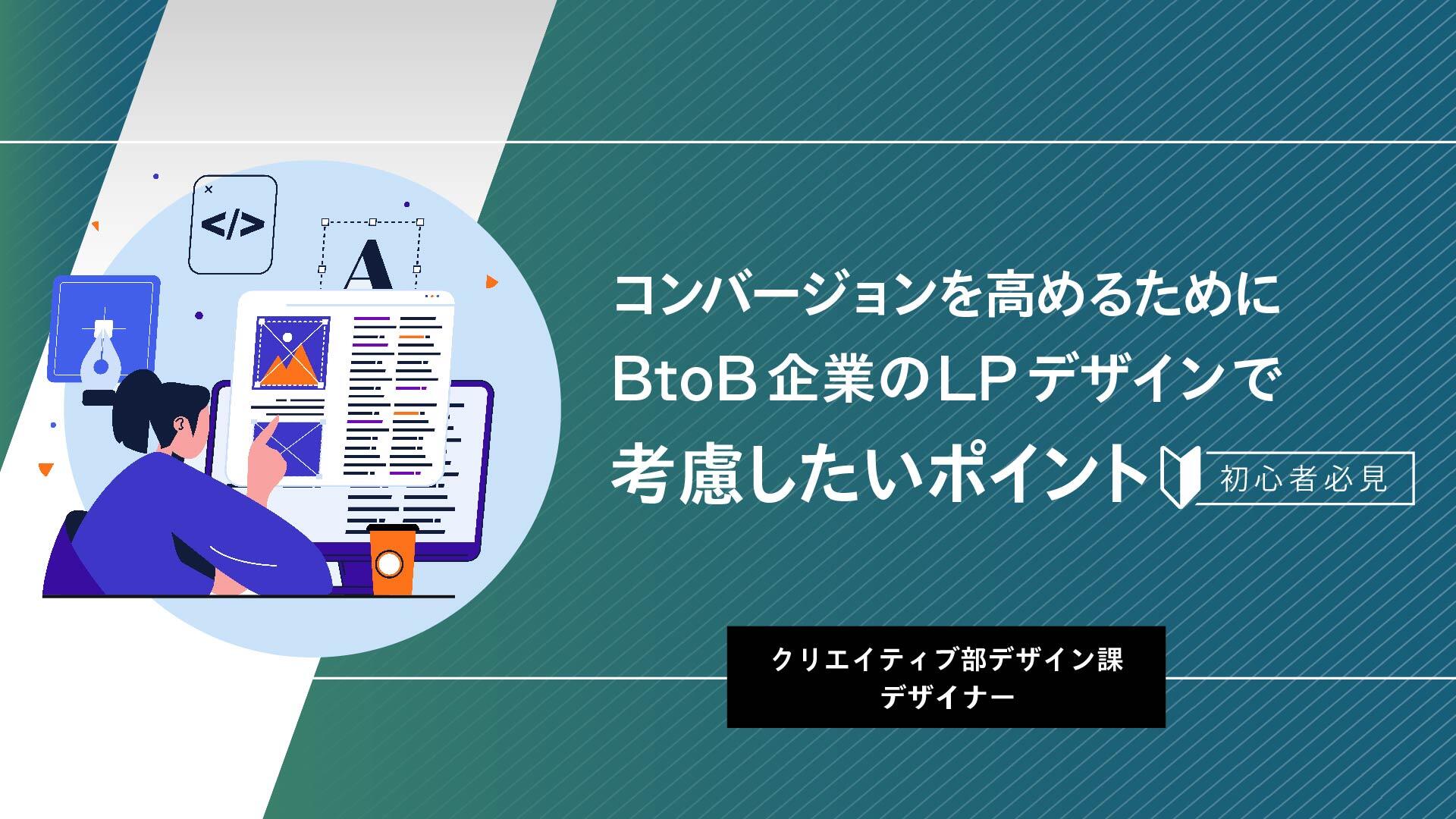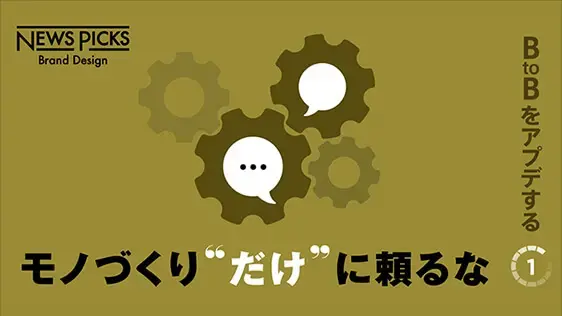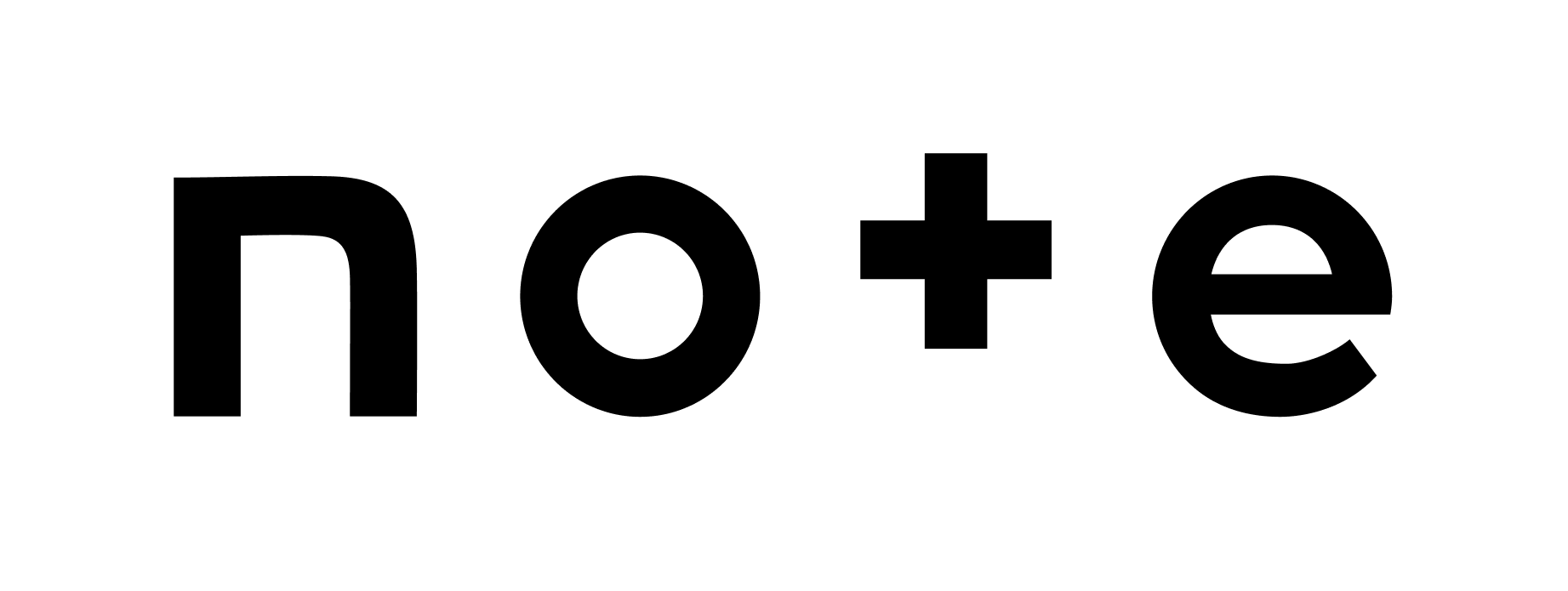画像フォントは、LPのファーストビューや見出しの部分によく使われます。見出しの階層が多いなど、メリハリがつきにくいような場合には、画像フォントを使うのも有効です。
画像フォントは、コンピュータにあらかじめインストールされているデバイスフォントと比較すると、装飾や大きさ、カラーなどを細かく設定することができるため、表現の幅が広いという特徴があります。
画像フォントはテキストとしての役割だけではなく、ビジュアルとしての役割も担うことができるため、見出しやファーストビューなど、ユーザーにインパクトを与えたい箇所で画像フォントを使うことで、よりメリハリのあるデザインが可能です。
本文のフォントサイズは16pxがおすすめ
LPやホームページなどで、文字が小さくて読みづらいな、と感じた経験はありませんか?フォントサイズが小さくて読みづらいと、離脱される確率が上がってしまい、コンバージョンに結びつきにくくなってしまいます。そのため、小さすぎる文字を使うことはお勧めできません。
フォントサイズとしてお勧めなのが16pxです。検索サイトの1つであるGoogle Chromeは任意に文字のサイズを設定できますが、標準の設定は16pxとなっています。こうしたことから、LPだけでなくコーポレートサイトやECモールなど、多くのサイトが16pxの本文サイズを使用しています。基本的には本文のフォントサイズは16pxにするとよいでしょう。
ファーストビューはLPの内容がひと目でわかるように
Webページを開いたときに画面に表示される画面を「ファーストビュー」と言います。ファーストビューでユーザーの関心を惹きつけられなければ、LPを下にスクロールしてもらえません。ファーストビューは、「もっと読みたい」と思われるようなデザインにすることが必須です。
「パケ買い」という言葉がありますが、ファーストビューをつくるときも、「このLPには何が書かれているか」がパッと見ただけでわかるようにデザインしましょう。
例として、ユーザーが商品を実際に使用している未来が連想できるデザインのほか、ユーザーの悩みを的確に表すコピーを強調させることによって、共感を獲得するデザインなどが挙げられます。さらに、サービスや商品の強みやメリットなど、ユーザーが最も知りたい情報をファーストビューに盛り込んで「結論から示す」デザインも有効です。
続きが気になるような工夫をする
ドラマやバラエティー番組では、CMで視聴者に離脱されないように、CMに入る前に謎を提示しておく、という編集がなされることがあります。視聴者はその謎が気になるため、続きを見たくなるわけです。
ファーストビューも同様です。次のトピックスの見出しだけ画面をスクロールしなくても目に入るようにするなど、続きが気になるようなデザインにすると、先を読み進めてもらえる確率が上がります。
コンバージョンボタンのデザインは統一させる
「お問い合わせはこちら」「セミナー申込みはこちら」など、コンバージョンを促すボタンのデザインは、コンバージョン率を左右する重要な要素です。
コンバージョンにつながる行動をユーザーに直接うながすための「CTAボタン」がLPの中で複数登場する際には、デザインは一つに統一しましょう。ファーストビューに表示されるコンバージョンボタンは赤、LPの最下部に表示されるコンバージョンボタンは青など、デザインを変えるのは避けるべきです。
ユーザーは、最初に目に入ったコンバージョンを「これがCTAボタンだ」と認識し、そのデザインを記憶します。そうすると、LP内で他の場所に似たようなボタンが登場したときにも「これもCTAボタンだ」と推測してくれるようになります。その結果、「コンバージョンはどれだったかな」と考えることなく、スムーズなアクションを促すことが可能になるのです。
CTAボタンをデザインするときには、心理的に「つい押してしまう」デザインにすることもあります。
例えば、目の前にボタン状の突起物がついた箱が置いてあったとしたら、ついその突起物を押してしまいたくなりませんか?それが一体何のボタンであるかを知らなくても、私たちは直観的に「押す」という行動を取りがちです。
それはLPなどのWebコンテンツであっても同様です。例えば、ボタンに立体感をつけるなど、ユーザーにその要素が“押せる”と感じさせるように工夫することで、コンバージョン率が上がることがあります。
立体感の他にも“押せる”をユーザーに感じさせる手法として、「ホバーエフェクト」を付けたり、影やアイコンを付ける方法などがあります。
このような「説明なしに使い方がわかり、人に自然な行動を促す工夫や効果」 のことを「アフォーダンス」と呼びます。アフォーダンスを意識したデザインは、言葉で訴求しなくともユーザーの行動を促す効果が期待できるのです。
入力フォームはユーザーのストレスを軽減するデザインに
アフォーダンスにも代表されるように、デザイナーは人間の心理についても理解を深めた上で、コンバージョンを高めるための工夫をちりばめてデザインを行っています。
これは入力フォームについても同じです。入力フォームは、これまで受動的にLPを閲覧していたユーザーが能動的に情報を書き込む動作をする場所です。また、コンバージョンを直接成立させる重要な役割を担っています。そのため、ユーザーがストレスなく情報を入力し、送信ボタンを押すというアクションを促すためのデザインが欠かせません。
ストレスを軽減するためには、できるだけ入力フォームをシンプルに見せる必要があります。細かいことですが、入力欄の左端をそろえることによって、手間のかかる入力作業もスムーズに感じる効果が期待できます。