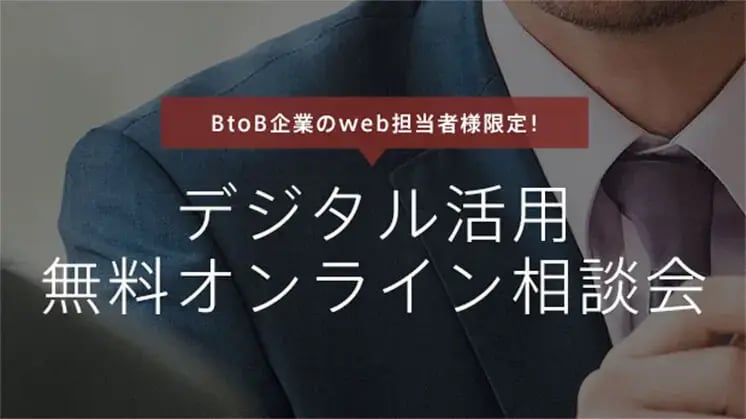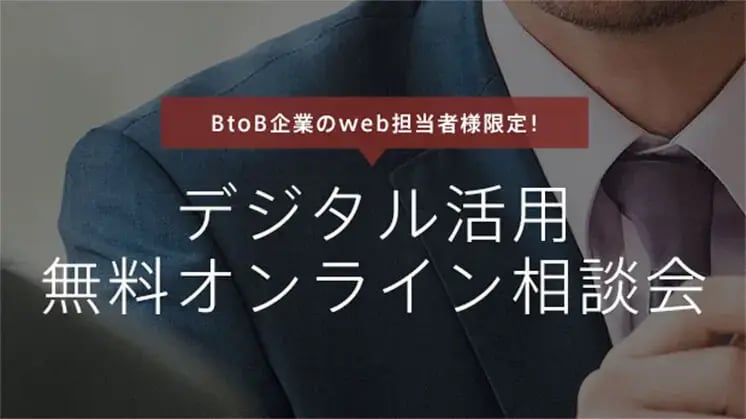経済産業省が目指すDX
次に、経済産業省が提示する具体的なDX施策を紹介します。
経済産業省が進めるDX推進施策
経済産業省が進めるDX施策には、次のようなものがあります。
- DXの「見える化」指標の策定・中立的な診断スキームの構築
- 「DX推進システムガイドライン」の策定
- ITシステム構築のリスク低減に向けた対応策
- ユーザ企業とベンダー企業の新たな関係構築
- DX人材の育成・確保
DXの「見える化」指標の策定・中立的な診断スキームの構築
1の「DXの『見える化』指標の策定・中立的な診断スキームの構築」については、前章で解説した「DX推進指標」をもとに対応を進めています。
DX推進指標の評価項目を決めるにあたって、20名以上の有識者が集まる全体会議を計3回実施しました。さらに、約10名の有識者によるワーキンググループ(WG)を計5回実施しています。
参照元:独立行政法人情報処理推進機構「『DX推進指標』とそのガイダンス(p.52-p.53)」
「DX推進システムガイドライン」の策定
2の『「DX推進システムガイドライン」の策定』については、「DX 推進における取締役会の実効性評価項目」を発表しています。
「DX 推進における取締役会の実効性評価項目」とは、取締役会が自社のDX推進状況を把握するためのチェックリストのことです。
チェックリストには、「DXに関する十分な知見や問題意識を持つ取締役を(少なくとも一名)選任しているか」「DX化による将来的な経営環境の変化について十分な議論が尽くされているか」などの項目があります。取締役会は、それぞれの項目に対して「強くそう思う」「そう思う」「そう思わない」「全くそう思わない」の中から回答を選択します。
「そう思わない」「全くそう思わない」の回答が多かった項目は、改善の余地があると判断できるでしょう。
ITシステム構築のリスク低減に向けた対応策
3の「ITシステム構築のリスク低減に向けた対応策」については、「DXレポート〜ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開〜」の中で詳述しています。
同レポートでは、ITシステムのリスク低減策として次の内容に触れています。
- 刷新後のシステムが実現すべきゴールイメージの共有
- 不要な機能を廃棄することの重要性
- 刷新におけるマイクロサービス等の活用
- 協調領域における共通プラットフォームの構築
引用元:経済産業省「DXレポート〜ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開〜(p.31)」
ユーザ企業とベンダー企業の新たな関係構築
4の「ユーザ企業とベンダー企業の新たな関係構築」については、ユーザー企業(※2)とベンダー企業(※3)が目指す姿をそれぞれ以下のように提示しています。
- ユーザ企業の目指すべき姿
- 既存システム上のデータを活用したDXが可能になる
- 新たなデジタル技術を活用し、ビジネスモデルを迅速に変革できる
- ベンダー企業の目指すべき姿
- 最前線のデジタル技術の分野で競争力を維持し続ける
- 以下の技術分野をリードする
(1)AIなどを活用したクラウドベースのアジャイル開発によるアプリケーションの提供
(2)ユーザ企業が行うアジャイル開発に対するコンサルティング
(3)最先端技術の提供など
- 受託業務から脱却し、クラウドベースのアプリケーション提供型ビジネスモデルに転換していく
- ユーザ企業とプロダクトを共同開発し、ユーザ企業以外の顧客にもプロダクトを販売していく
※2 消費者向けの事業を展開している会社のこと。
※3 販売会社のこと。
参照元:経済産業省「DXレポート〜ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開〜(p.34)」
DX人材の育成・確保
5の「DX人材の育成・確保」については、次のような対応策を示しています。
- アジャイル開発を実践する
- 情報処理技術者試験の活用などにより、IT人材に必要なスキルを明確化する
- 大学などの教育機関でIT人材の育成を進める
参照元:経済産業省「DXレポート〜ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開〜(p.38)」
企業が取り組むべきDX
企業が取り組むべきDXには、大きく分けて以下の3つがあります。
- DXに取り組む目的を明確にする
- IT人材を育成・確保する
- 「オープンイノベーション」を取り入れる
DXに取り組む目的を明確にする
まずは、DXを進める目的を定めることが重要です。
DXの目的を「業務の効率化」とした場合、「勤怠管理・経費精算システムを導入する」「書類の締結にクラウドサービスを活用する」などの施策が考えられるでしょう。
自社の目的に沿って施策を決めることで、納得感をもってDXを進められるはずです。
IT人材を育成・確保する
次に大切なのが、IT人材の育成と確保です。
IT人材を一から育てるためには、多くの時間と費用が必要になります。
数年後に戦力として活躍してもらうことを目標に、今のうちから人材育成を始めるとよいでしょう。
社内での人材育成が難しい場合は、一部の業務を外注するのもひとつの方法です。
「オープンイノベーション」を取り入れる
新しい意見を取り入れるために、「オープンイノベーション」を活用するのがおすすめです。
オープンイノベーションとは、社内外のさまざまな知見を活用し、自社で生まれたイノベーションを社外に共有することです。
社内の知見だけでは解決が困難な問題も、社外の知見を取り入れることで解決の糸口が見つかるかもしれません。
問題解決の引き出しを増やすために、社内外を問わず意見を求めることが大切です。