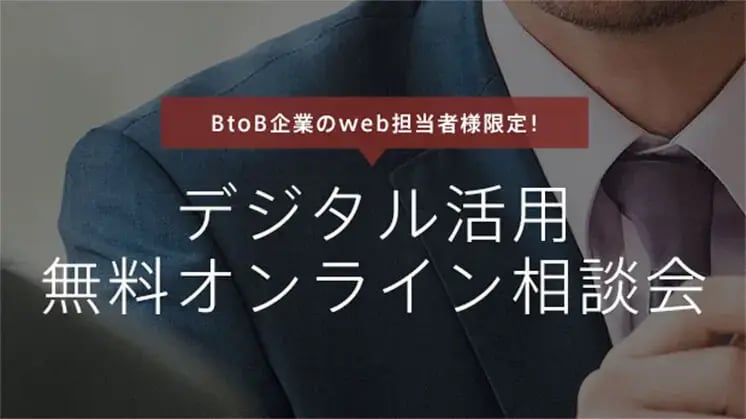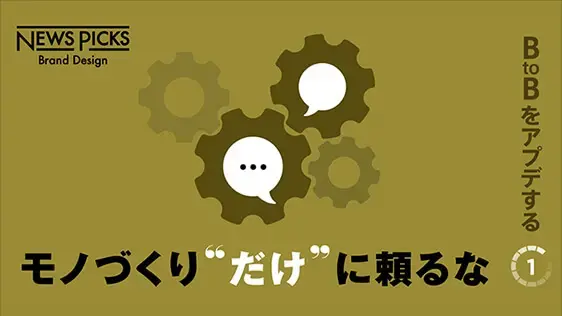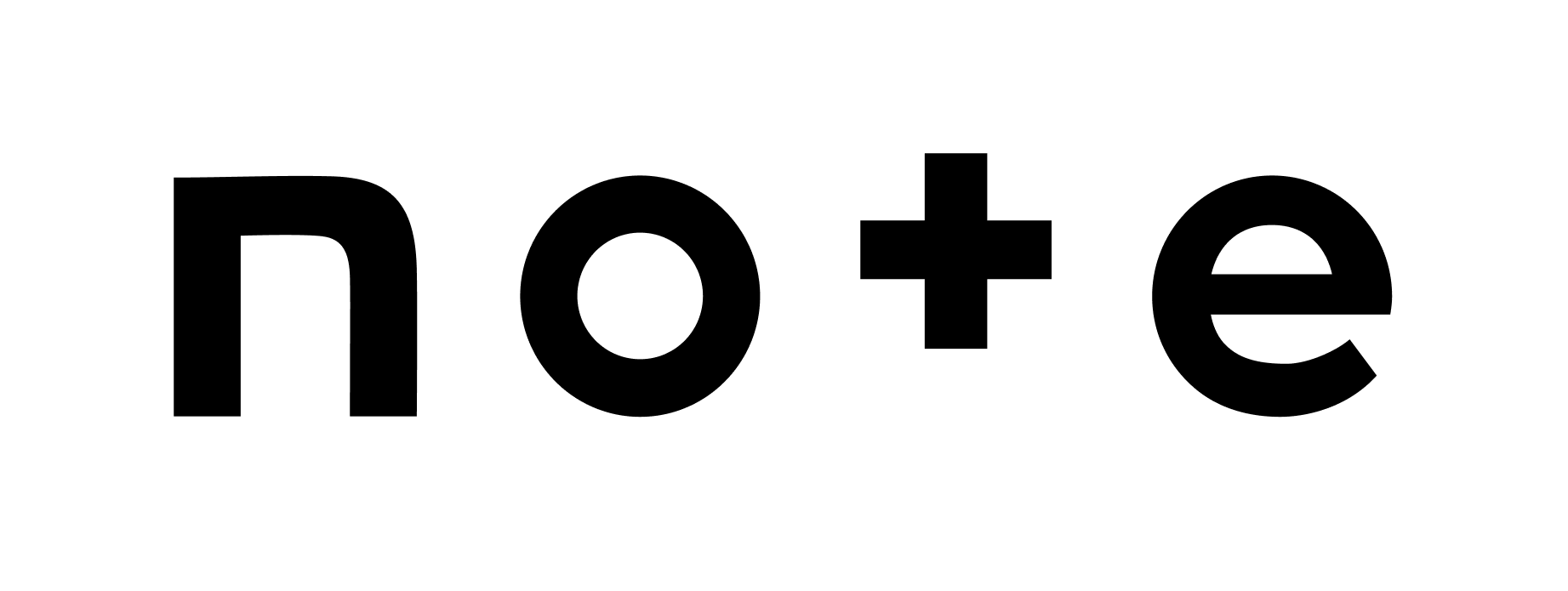BtoBにおける見込み顧客獲得から受注までのフレームワーク
BtoBマーケティングにおける代表的なフレームワークに、SiriusDecisions社が発案した「デマンドウォーターフォール(Demand Waterfall)」があります。デマンドウォーターフォールは、リードから最終的な売上に至るまでの一連のステージを可視化するフレームワークで、マーケティングと営業のプロセスを整理し、効率化するために使用されます。リードの生成から育成、クオリフィケーション、そして最終的な売上までのプロセスを視覚的に表現し、マーケティングと営業チームが共通の理解を持つことを目的としています。
BtoCでは、マーケティングの流れを認知→興味関心→行動に分類する「AIDMA」「AISAS」などのフレームワークが代表的です。
デマンドウォーターフォールでは、マーケティングの流れを以下の5つの段階に分けています。
- Inquiries(問い合わせ)
- Marketing Qualified Leads(MQL)の獲得
- Sales Accepted Leads(営業担当が受け入れた見込み顧客)の獲得
- Sales Qualified Leads(SQL)の獲得
- Close/Won business(商談/成約)
デマンドウォーターフォールを理解して活用することで、MQL・SQLの獲得を含めたBtoBマーケティングの流れが理解しやすくなります。また、 各ステージでのパフォーマンスを可視化して測定することでボトルネックや改善点を特定でき、営業活動全体の最適化にもつながります。
単価が高く、担当者や決裁者が複数名にわたるBtoB製品では、成約までの検討期間が1年以上になることがよくあります。
長い期間をかけて慎重に契約の有無を検討するBtoB製品のマーケティングでは、各部門の担当者との連携も同時に重要です。デマンドウォーターフォールの5つの段階ごとに、各部門から最適な専門スキルのリソースをアサインし、顧客を成約に導いていきましょう。
MQLを受注につなげるための成功ポイント
ここまでの解説で「BtoBマーケティングのフレームワークやMQL/SQLの違いは理解できたが、具体的にはどのように実践していくのか」と疑問を感じている方もいらっしゃるかもしれません。そこで、見込み顧客の獲得からMQLの創出という「0から1」のステップを担うマーケティング担当者に焦点を当てて、受注につながる質の高いMQLを獲得するためのポイントをご紹介します。
1. 自社の製品・サービスを広く認知してもらう
BtoB製品はBtoCと比較してターゲットの母数が圧倒的に少ないため、マーケティングも非常に難しく工程も複雑になります。そのため、最初から見込み顧客を絞り込みすぎず、自社製品を広く認知してもらうことからスタートすることが重要になります。
業界や役職を絞り込みすぎず、まずは自社製品やサービスの存在を知ってもらうこと・自社製品に少しでも関心を持ってくれたユーザーの個人情報を集めることに集中し、見込み顧客の精査はそのあとに行いましょう。
「認知を広める」ためにはオフライン・オンラインにそれぞれの施策があります。オフラインでは展示会への出展やセミナー、イベントの開催はリアルイベントへの協賛など、オンラインでは、Web広告への出稿やSEOコンテンツの作成、メルマガの配信やウェビナー開催などが代表的なマーケティング施策です。
マーケティング予算や人員、目標到達までのスケジュールという社内事情を踏まえながら、商品の特製やターゲットなどニーズに合わせてマーケティング活動を使い分けましょう。
2.MQLの判断基準を定める
次に行うべきなのが、MQLの定義をマーケティング担当と営業担当でしっかりとすり合わせることです。BtoBマーケティングは基本的に他部門を巻き込んで行う必要があるため、最初の認識が間違っていたり、当初のターゲットに効果がなく実情とずれているなどに気がつかないとマーケティング活動だけでなく営業活動にも大幅な損失が生じます。
マーケティング担当のみでMQLを設定した場合、営業担当の求める基準に達していなかったり、そもそもかけ離れている場合も考えられます。そのため、マーケティング活動を始めるタイミングで、インサイドセールスや営業などの他部門を巻き込み、ターゲットの業界・業種やニーズなどをすり合わせ、ターゲットの解像度が高まった状態でMQLの定義を行いましょう。これにより営業担当に引き渡す時点での認識のズレが生まれにくくなり、マーケティング全体がスムーズに進みます。
MQLの創出の目的はあくまで営業活動の円滑化の支援のため、「営業担当が求める条件を満たしているか」という観点でMQLの判断基準を設定することで、より効果的な営業の支援が実現します。
3. 営業担当からフィードバックをもらう
営業やインサイドセールスなどとすり合わせて一度MQLの定義が決定しても、それで終わりではありません。営業活動が始まる前に設定したMQLが、実際に様々なアプローチを始めてみるとそこまで反応を得られない場合も考えられます。
このように当初に設定したMQLが正しいとは限らないため、半年・1年・1年半などのスパンに区切って、「この期間までに商談や受注につながっていなければ検討度合が低い」と判断することが大切です。その上で、各期間までに期待する行動が見られなかった見込み顧客を営業担当から共有してもらい、ある程度の共通点が見つかった時点でMQLの再定義を行いましょう。「受注したMQL」だけではなく「受注しないMQL」の精査を定期的に行い、「この属性はいくらアプローチしても受注に繋がらない」ということを判断することも重要です。
検討期間が長いBtoB製品という特性上、「検討期間が延びているのか、それとも検討度合が下がっているなのか」を見極めることで、確度の高い見込み顧客にアプローチの時間を十分に割けるようになります。
部門間の連携を怠ると、各フェーズでの成功事例や失敗事例が共有されず、MQLの質の低下や失注につながりかねないリスクがあります。特にBtoBの製品・サービスは検討期間が1年以上になることもあるため、定期的かつ効果的なアプローチを行う必要があります。商談中の顧客は、社内で話し合ったり他社の情報収集もしながら検討しているため、MQLへのアプローチを怠ったり間違えると、競合他社の製品・サービスに流れてしまう可能性が高くなる危険性をよく理解しましょう。