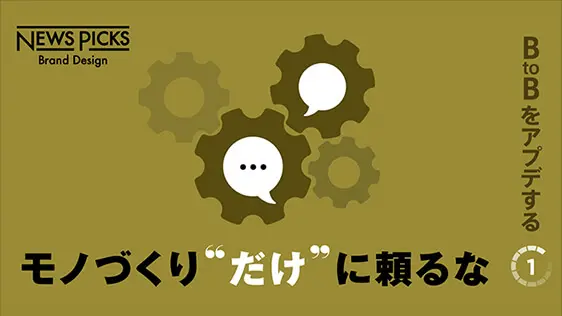- ブレッドクラム
-
- HOME
- BtoBマーケティングコラム
- BtoBマーケティングで戦略立案に活用できるフレームワーク11選と使い方を解説
BtoBマーケティングコラム BtoBマーケティングで戦略立案に活用できるフレームワーク11選と使い方を解説
2023年4月6日

Index
BtoBマーケティングのフレームワークとは
フレームワークとは、頻繁に用いられる考え方をパターン化して用いることを指します。
BtoBマーケティングにおけるフレームワークとは、ビジネスを進めるうえで便利な考え方をまとめた枠組みのことです。事業の現状分析、投資判断の意思決定、戦略立案など、さまざまな場面に応用できるフレームワークが考案されています。
フレームは「枠」を意味しますが、フレームワークの存在を知っておくと、BtoBマーケティングに着手したいが何からはじめたらよいのか分からない、というときにも便利です。
フレームワークは何度も使うことで考え方が身についていき、マーケティング活動を効率的に進めることが可能になります。
今回は調査や企画、戦略立案をする際に有効活用できるフレームワークをご紹介します。
BtoBマーケティングの調査や施策の企画で使用するフレームワーク6選
先ほどご説明したように、フレームワークにはビジネスの各場面に応じたさまざまなフレームワークがあります。
ここでは、市場や競合の調査、マーケティング施策を企画する際に便利なフレームワークを6つご紹介します。
STP分析
STP分析は、マーケティング施策を実施する狙いを定める際に役立つフレームです。STPはそれぞれ
- Segmentation(セグメンテーション)、
- Targeting(ターゲティング)、
- Positioning(ポジショニング)
の頭文字を表しています。分析を進める順番に並んでいるため、フレームワークの使い方も比較的覚えやすいでしょう。
マーケティングは、限られた資金や時間を有効活用して利益を向上させるために、力の注ぎどころを見極める作業でもあります。STP分析を活用すると、どのような属性をもつ企業あるいは購買者(バイヤー)を顧客とし、自社に対してどのような印象を抱いてもらうのかという方針を定めることができます。
STP分析の使い方
まずは、自社が参加している市場を細分化する軸を定めます(セグメンテーション)。
細分化した市場のうち、どこに属する企業にアプローチするのかを検討します(ターゲティング)。
狙いを定めた企業には競合企業もアプローチしているはずなので、自社はそのなかでどのような価値を発揮するのかを企画していきます(ポジショニング)。
STP分析はセグメンテーションする際の切り口が重要です。都心・地方、中央アジア・ヨーロッパといった地理的な切り口、年齢や所属企業におけるポジションのように人に焦点を当てた切り口などがあります。
3C分析
3C分析は自社をとりまく状況を俯瞰する際に役立つフレームワークです。Company(自社)、Customer(顧客)、Competitor(競合)の3つの観点から状況を分析します。
マーケティングに限りませんが、何かしらの有効な企画を立てるには現状の分析が欠かせません。自社、顧客、競合、3つの観点から現状分析を行うことによって、企画立案を進める土台を整えることができます。ビジネスを行う際に必ず関わってくる3つの要素について分析するため、いったん視野を広くするためのフレームワークともいえるでしょう。
市場のニーズに対して自社の商品・サービスがどのように応じているのか、競合企業はどのような戦略をとっているのかを把握しながら整理を進めます。
3C分析の使い方
まずは顧客や市場全体のニーズ、市場規模などマクロな視点から分析をはじめます。その後に自社や競合についての分析を進めていきます。
自社の分析は、商品・サービスの売上高や特徴、組織内の人材などから自社の強み・弱みを発見していきます。競合の分析では競合の商品・サービスの特徴のほかに売り方などの戦略面も調査します。
参加している環境を俯瞰した上で、自社や競合企業について分析を進めていくことがポイントです。自社が提供している価値は何なのか、競合企業に勝っているポイントは何か、現状への理解が深まることで今後に取るべき施策が見えてくるようになります。
4P
4Pは、Product(製品)、Price(価格)、Place(流通)、Promotion(販促)の4つの要素を意味します。企業の活動において、企業側が操作可能な要素のうち代表的な4つを表したものになります。
4Pのフレームワークは、現状から何かしらの変更をかけていく際の目安となります。またマーケティング施策をこれら複数要素の組み合わせとして捉えることをマーケティング・ミックスといいます。
例えばニーズを分析して「Product」を改善しても売上に変化がない場合、「Promotion」の方法も変えることで魅力が伝わるようになるのではないか、といった仮説が立てられます。
4Pはマーケティングの観点を4つに分けたシンプルなものですが、強力なフレームワークです。
4Pの使い方
マーケティング施策を検討する際に、どの要素に変更をかけていくのか考える際に活用します。企画会議を行う際などに、関係者間で事前に4Pの観点を共有しておくと視点がブレることなく進められるかもしれません。
製品自体に変更を加えるのか、価格を変えるのか、販売する場所や流通経路を変えるのか、見せ方や伝え方を変更するのか、以上の観点から検討を進めます。このとき、どの要素を変更したのか振り返れるように記録をつけることをおすすめします。
4Pのフレームワークは、変更前後を比較できる仕組みを整えつつ運用すると良いでしょう。
マーケティングファネル
マーケティングファネルは、顧客が商品・サービスを認知してから購買するまでの行動を段階分けしたモデルです。スマートフォンやSNSの普及に伴い、消費者が情報発信できるようになってからは、購買後の発信も視野に入れたマーケティングファネルも登場しました。
大きくは認知から購買までを段階分けした「パーチェスファネル」と、購買後の口コミや情報発信を段階分けした「インフルエンスファネル」とに分けられます。また両者を組み合わせた「ダブルファネル」というフレームワークもあります。
マーケティングファネルは顧客の購買行動をモデル化したものですが、顧客の検索・購買行動の複雑化に伴って顧客分析には向いていないといわれているようです。
マーケティングファネルの使い方
顧客分析への適応は難しくても、自社のマーケティング施策において何を強化するかという観点で、マーケティングファネルは有効です。
例えばパーチェスファネルは認知・興味関心・比較検討・購入の4段階にわかれますが、これに基づいて自社のマーケティング施策を分類することができます。
またマーケティングファネルによる分類にしたがって「認知度を拡大する」「問い合わせの数を増やす」「受注率を向上させる」といった目標を立てることも可能です。サブスクリプション型のサービスの場合、解約率を目標として定めることもできるでしょう。
LTV分析
LTVは評価指標のひとつで、とくにサブスクリプション型の商品・サービスを提供する企業において重要なものです。Life Time Valueの略称で、一人の顧客が契約開始から契約終了までに支払うお金の総額を意味します。
例えば、月額課金のサービスを提供している場合
顧客一人あたりの単価 × 利益率 × 平均的な契約継続期間 = LTV
上記の計算式で表すことが可能です。
LTVの計算式に決まりはないため、それぞれの組織で納得のいくものを定めることをおすすめします。上記の場合、契約獲得までのコストを導入することも可能です。
LTVの最大化を目標に置くと、新規契約だけではなく継続にも重きが置かれるため、ノルマ達成のために契約を急ぐことがなくなる効果も期待できます。
LTV分析の使い方
LTVはフレームワークというよりは評価指標のひとつのため、マーケティング施策を検討する際のKGI・KPIを定める際に用いられます。
KGIはKey Goal Indicators の略で、施策を評価する最終的なゴールを意味します。
KPIはKey Performance Indicatorsの略で、KGIを達成するために欠かせない中間指標にあたります。
KGIにLTVを設定すると、KPIには解約率や新規顧客のひとりあたりの獲得コストなどが挙げられます。KGI・KPIに何を設定するかで組織の動きも変化するため、評価指標の設定も重要なマーケティング業務のひとつです。
VRIO
VRIOは4Pのように、分析の際に用いる4種類の観点を表しています。それぞれValue(経済的な価値)、Rarity(希少性)、Imitability(模倣可能性)、Organization(組織)の頭文字をとったもので、自社の強み・弱みを把握することに適したフレームワークです。
Valueは市場のニーズや脅威にどれだけ応えられるか、Rarityは類似製品・サービスの少なさ)を意味します。Imitabilityでは「真似されやすさ」を見て、希少性があっても真似されやすければ、それは一時的なものに過ぎないと判断するような指標です。Organizationでは、分析対象とした経営資源を運用できる組織体制が整っているかを評価します。
VRIOの使い方
分析を進める順序はV→R→I→Oの順番で、はじめに分析対象とする経営資源を定めます。経営資源には人材、技術、これまでの活動により培った販路などが挙げられます。それらについて、RarityやImitability、Organizationの観点から評価を進めていき、自社の競合優位性がどの程度なのか、それはどれくらい継続し得るのかを判断します。
VRIO分析には、その前段として市場を細分化する作業が入ることにも気をつけましょう。STP分析の「セグメンテーション」「ターゲティング」のあとに取り組むことで経営資源を定めやすくなるはずです。
BtoBマーケティングの戦略を考える際に使用するフレームワーク5選
ここまでは市場や競合の調査、マーケティング施策を企画する際に便利なフレームワークを紹介しました。
ここでは、戦略立案に便利なフレームワークを5つ紹介します。特徴を把握して、目的に適ったフレームワークを選択できることを目指しましょう。
5F
5Fを簡潔にいうと5種類のForce(脅威)です。自社が参加しているもしくは参加を検討中の市場にある5つのForceを評価することで、市場の魅力や競争の厳しさを見極めるためのフレームワークです。
5つのForceとは、
- 競合の脅威
- 新規参入の脅威
- 代替品の脅威
- 売り手の脅威
- 買い手の脅威
の5つです。
「競合の脅威」は競合他社の数や新規参入のしやすさ、買い手や売り手(仕入元など)が価格交渉においてどれだけ力を持っているか、といった観点から市場を評価します。
新規参入を検討するケースでは、STP分析の市場を細分化する工程である「セグメンテーション」と組み合わせることで、参入か見送りかを考えやすくなるでしょう。
5Fの使い方
5Fには所定の分析方法があります。
まず「競合の脅威」を中心に置き、「新規参入の脅威」「代替品の脅威」を上下に配置します。
続いて、「競合の脅威」の左右に「売り手の脅威」と「買い手の脅威」を配置して、該当する情報を記入していきます。
例えば製造業で特許技術を取得している企業であれば、新規参入や競合の脅威はあまり大きくはないでしょう。しかし別の市場から代替品が登場する可能性もあるため、そのような技術や製品がないか調査を行うことで脅威の度合いが図れます。
また別の例では、製品の買い手が1つの企業に大きく依存している場合は「買い手の脅威」が大きいと判断できます。
上記のように、5Fのそれぞれについて調査も視野に入れながら分析を進めます。
PEST分析
PESTはそれぞれPolitics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の頭文字をとったものです。
4Pのように4つの視点を提供するフレームワークですが、他のものより巨視的・長期的な視点でものごとを捉えるものです。市場を細分化したり、その市場を評価したり、自社の強み・弱みを把握していくものとは異なり、社会の動向と自社の経済活動との関係を見ていくようなフレームワークです。
現状把握よりも、5年後や10年後における社会の変化を予測したり、予測した変化への対応方法を検討したりといった用い方をします。かなり大きな視野をもって自社の置かれた環境を見渡すイメージをもつと良いかもしれません。
PEST分析の使い方
2023年現在では、アフターコロナの社会やAIの動向が自社にどのような影響を与えるのかを考えていくことがPEST分析に該当するでしょう。その他には労働力となる人口の減少も挙げられます。
輸出入を頻繁に行う企業であれば為替の動き、国際関係へ視点をずらすとロシア・ウクライナ間の戦いが今後どうなるのかを予測していくことも挙げられます。このように、今後の社会動向を見据えた内容を経営の検討材料とすることがPETS分析の主眼です。最初は自社と関係の深いものから着手すると取り組みやすいでしょう。
SWOT分析
SWOTはそれぞれ、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の頭文字をとったものです。このフレームワークは、自社の内部に存在するもの/外部に存在するものという軸と、ポジティブ/ネガティブの軸をかけ合わせることで生まれる4つの象限に情報を置き、SWOTのそれぞれを発見するものです。
例えば、内部×ポジティブ(独自の製造技術を有しているなど)はStrengthに分類され、外部×ポジティブ(IoT需要の増加など)はOpportunityとして分類されます。
このように、自社の内外にある情報を4つの象限に配置していき、ビジネスチャンスや改善すべき点などの発見につなげることがSWOT分析の目的です。
SWOT分析の使い方
内部/外部、ポジティブ/ネガティブをかけ合わせたマトリックスを用意し、そこに情報を記入していくかたちで分析を進めます。
STP分析を応用してセグメンテーション→ターゲティングと進めていくように、俯瞰的な視点から始めると情報を集めやすくなるでしょう。
内部については経営資源を見つめていくVRIOを用いながら人材や技術など、これまでの事業活動で蓄積されたものや課題を棚卸しすると強み・弱みをバランス良く集められるかもしれません。ネガティブ/ポジティブの軸については見方を変えると反転する可能性も考慮しながら進めることがポイントです。
バリュープロポジション・キャンバス
自社の参加しているあるいは参入を検討中の市場において「競合には無い提供価値」を明らかにするためのフレームワークです。「競合にはない提供価値」のことをバリュープロポジションといいます。
顧客のニーズが達成されるにあたって「得たいこと」「避けたいこと」と、自社の提供する商品・サービスとの対応関係を発見することを目指します。他のフレームワークとの関係でいえば、STP分析の「P」を進める際に活用できることが特徴です。
また関係の近いフレームワークに「ビジネスモデル・キャンバス」があります。バリュープロポジションを含んだビジネスモデル全体を見渡せるもので、併用することでマクロ視点・ミクロ視点を往復しながら分析を進められます。
バリュープロポジション・キャンバスの使い方
まずは顧客のニーズについて、Job(課題)を定めたあと、課題が解決されるにあたってGains(得たいこと)、Pains(避けたいこと)をキャンバスに記入していきます。その後、それらに対応する自社の商品・サービスを記入していく手順で作成します。
ポイントは、顧客のニーズを起点として作成することです。自社の商品・サービスが提供し得る価値を分析するフレームワークですが、顧客のニーズを明確にしたあと、それらに対応している価値を発見するように進めます。対応関係が見つけられない場合は、提供している商品・サービスに改善の余地ありと判断できるでしょう。
PPM分析
Product Portfolio Managemenの頭文字を取ったもので、自社の経営資源の配分を検討する際に役立つフレームワークです。
市場成長率と市場占有率の軸を組み合わせたマトリックスを作成し、Star(花形)、Cash Cow(金のなる木)、Problem Child(問題児)、Dog(負け犬)の4象限を用いた分析を行います。
Starは市場成長率と市場占有率の両方が高い事業、Cash Cowは市場成長率が横ばいで市場占有率の高い事業、Problem Childは市場成長率は高いが市場占有率の低い事業、Dogは市場成長率・市場占有率ともに低い事業にあたります。
自社事業の状態が明確になり、資源配分の判断を行いやすくなる特徴があります。
PPM分析の使い方
市場成長率と市場占有率を算出し、その数値をもとに自社事業をそれぞれの象限に配置するかたちで分析を行います。市場規模は「市場規模マップ」のようなWebサイトや政府の統計資料などを活用すると把握しやすいでしょう。
市場占有率は、自社だけでなく競合企業のものも算出することで自社の立ち位置がより明確になります。例えば自社の市場占有率が5%と算出された場合でも、40%を超えるような大企業が存在するか多くの企業が10%程度の市場占有率を争っているかで投資判断は変わってくるでしょう。
-
参考サイト
市場規模マップ
フレームワークを活用するBtoBマーケティングの戦略立案の流れ
ここまでは調査や企画、戦略立案におすすめなフレームワークをご紹介してきました。続いてフレームワークを用いながら戦略立案を進める大まかな流れをご紹介します。事業戦略あるいは部門レベルの戦略立案としてご覧ください。
1.現状分析・競合との比較
マーケティング戦略を立案するには、自社の置かれた状況を正確に把握することが重要です。自社の状況を感覚的に把握しているつもりでも、多くの場合その内容はメンバーごとに異なるでしょう。
現状分析に取り組むことは、自社の状況を客観的に把握することはもちろん、メンバー間で共有することによって戦略立案の議論を進めやすくすることにもつながるのです。
分析は、マクロ視点から進めることが無難です。3C分析のフレームワークを活用しながら、自社、顧客、競合についての分析を進めていきましょう。現状分析には、SWOTのフレームワークも有効です。視野をさらに大きく広げたいときはPEST分析も活用できます。
2.戦略立案
現状分析によって見えてきた課題や活かすべき機会に基づいて戦略立案を行います。実際には現状分析を進めながら戦略のアイデアを記録していくかたちになるかと思います。この段階では、STP分析が有効です。
自社の参加している市場について把握しているつもりでも、細分化し図解化・言語化することで初めて分かることもあるでしょう。フレームワークを有効活用することで、認識のズレを防ぎながら議論を進めることが可能になります。
対象とするターゲットに対してどのような価値を提供するのかを定めたうえで、取り組むべき課題の優先順位や施策の評価指標などを定めます。当記事ではご紹介しておりませんが、評価指標の整理にはKGI・KPIツリーの作成がおすすめです。
3.戦略策定
優先順位や評価指標を定めた戦略を実行するための計画を作成します。目標をいくつかのプロジェクトに分割し大まかなスケジュールを引き、予算や必要な人員について検討します。
戦略立案で定めたそれぞれの課題について、どのような状態を目指すのか、いつまでに目指すのか、幾らくらいの予算で実行するのかを決定していきます。戦略立案で定めたターゲットと自社の提供価値の関係について改めて整理することもあるでしょう。
ターゲットと自社の商品・サービスの関係を整理するのにはバリュープロポジション・キャンバスが有効です。また戦略の方針や目標を忘れてしまわないよう、議論に用いたフレームワークは必ずドキュメントに残すようにしましょう。
4.評価・改善
戦略立案〜戦略策定で立てた計画や評価指標に基づいて、実行結果を振り返ります。基本的にはKGIやKPIの達成度などに基づいて、計画の修正が行われるかと思います。
振り返りの観点はさまざまなものがありますが、現状分析が正しかったかどうかを振り返るとフレームワークをより上手に使えるようになるでしょう。
また計画時に想定できておらず、実行時に初めて分かったことを「計画時に不足していた視点」として洗い出すことで、現状分析や戦略立案時に作成したフレームワークのドキュメントを修正することも可能です。
修正したドキュメントに基づいて、新たな戦略が見つかることもあるかもしれません。はじめに作った計画には調整が図られることを前提としながら、実行・評価・改善のサイクルを回せることが理想的です。
BtoBマーケティングの戦略立案で注意すること3つ
BtoBマーケティングの戦略立案に決まった方法はありませんが、成功させるために注意するべきポイントは存在します。
ここでは特に大切な3つのポイントをご紹介します。
他社と差別化できるポイントを明確にする
BtoBマーケティングの根本的な狙いは継続的な利益を発生させることです。現状分析ではその狙いに貢献しうる自社ならではの強みを発見することを重視しましょう。
ただし「弊社にはこのような強みがあるはずだ」という思い込みではなく、いま起きている事実や競合企業との比較に基づいた「仮説」として洗い出すように注意しましょう。
3C分析の自社・顧客・競合の視点、SWOT分析の強み・弱み・機会・脅威の視点などを活かしながら、他社と差別化できるポイントを明確にしていきます。競合との相対的な立ち位置を把握する意識で臨むと良いかもしれません。
ターゲットを明確にする
他社と差別化できるポイントがあったとしても、それが顧客のニーズに合致していない限りは利益の発生にはつながりません。ターゲット層を明確にすることは、自社の強みを明確にすることと同じくらい重要です。限られた経営資源をどこに投じるのかを定める作業でもあります。
ターゲットを明確にするのに有効なフレームワークは、STP分析です。自社の定めたターゲットには競合企業が存在するため、差別化ポイントを発見してポジショニングすることで継続的な利益の獲得を目指します。
実現可能な戦略を立てて実行する
アイデアを出す段階では考慮しなくてもかまいませんが、計画時には実現可能性を考慮する必要があります。予算や確保可能な人員、目標を達成したい期限に従って実現可能性のある戦略を絞り込み、実行計画を立てていきます。
いつ・どこで・だれが・なにを・どのように、といった風に5W1Hの要素を埋めていくようにすると整理が進みやすくなります。ここに「いくらで」と予算の観点も追加することでさらに整理が進みます。
検討の結果どのアイデアも実行が難しいことが判明した場合、戦略立案の段階からやり直す必要があります。無理に進めず調整を図ることが大切です。
まとめ
フレームワークは考え方の枠組みや視点を提供してくれるもので、それぞれに得意・不得意があります。フレームワークを使う際に覚えておきたいのは「繰り返し使うことで身につく」ことです。それらを1回で把握することは難しく、使い方や使いどころを覚えるには時間が必要です。
BtoBマーケティングにフレームワークを取り入れる際は、初心者だけでおこなわず、使い慣れている方を最低でも1人は置くことをおすすめします。どのような視点を提供してくれるものなのか、他のフレームワークとはどのように関連しているのか、使いながら理解を深めていくと良いでしょう。
イントリックスでは、お客様のビジネス視点からデジタルマーケティングの戦略立案から施策実施までをご支援しています。ビジネス課題の整理や関係者へのヒアリングによって、現在のマーケティングプロセスを可視化。加えて、ターゲット顧客の定義と提供すべき価値の具体化と、保有コンテンツの棚卸しを通じて、企業におけるデジタルマーケティングのあるべき姿とロードマップを策定します。これにより、関係者を巻き込み、実行段階に向けたスムーズな合意形成を実現します。
デジタルマーケティングをご検討の際には、ぜひ一度イントリックスへお問い合わせください。
BtoB企業のデジタルコミュニケーションを総合的に支援しています
BtoB企業に特化したサービスを提供してきたイントリックスには多くの実績とノウハウがございます。現状のデジタル活用の課題に対し、俯瞰した視点でのご提案が可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
お問い合わせ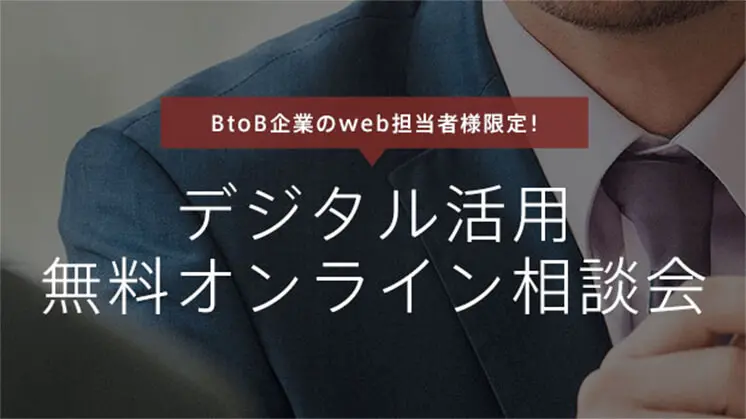
デジタル活用 無料オンライン相談会
BtoB企業のデジタル活用を支援してきた各分野の経験豊富なコンサルタントが、マクロな調査・戦略立案からミクロなデジタルマーケティング施策まで、デジタル活用の悩みにお応えします。
無料オンライン相談会概要・お申し込み

NewsPicks掲載「BtoBをアプデする」
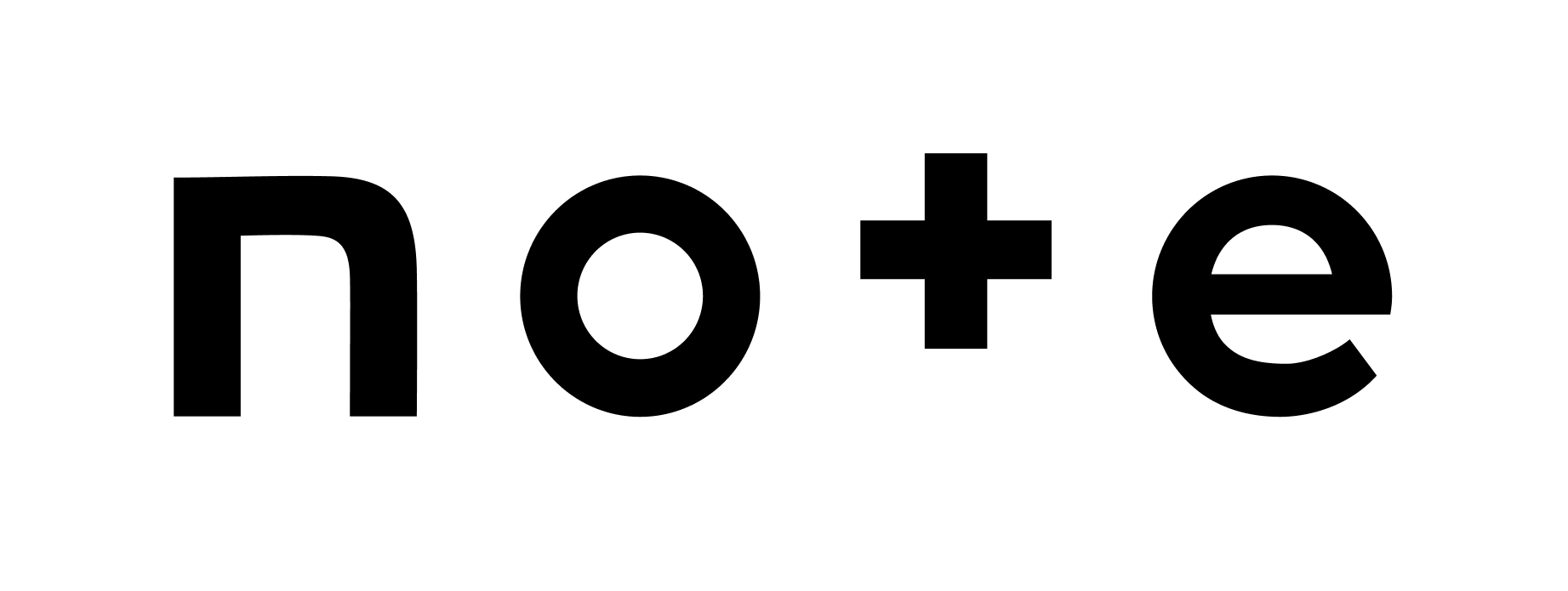
イントリックス代表 気賀 崇の公式note
noteでは、BtoBのデジタルコミュニケーションの面白さや意義、可能性などについて語っています