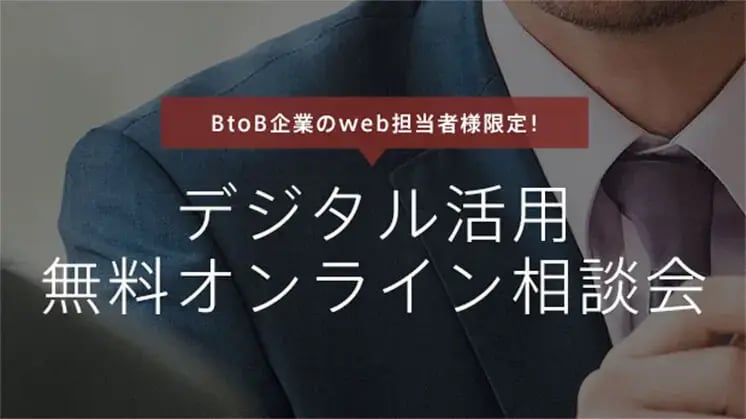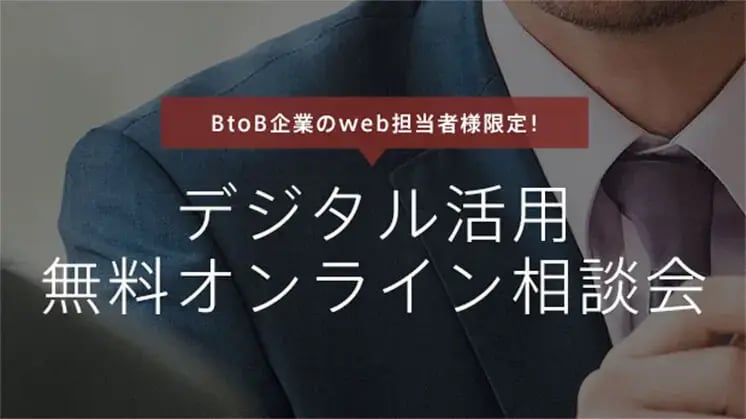なぜDX人材育成が求められるのか
DX人材とは「デジタル技術を活用した経営戦略を描ける人材」のことを指します。
DX人材は業務効率化だけでなく、情報資源を活用して新たな価値を創造するためにも欠かせません。
しかし、多くの企業ではDX人材を社外に頼っており、自社内で人材育成をできていないのが現状です。
みずほ情報総研株式会社の「IT人材需給に関する調査」では、2030年に最大で79万人のDX人材が不足すると報告されており、経済産業省ではDX人材不足を大きな課題として挙げています。また、転職市場でもDX人材は慢性的に不足しているため、自社内でのDX人材育成が急務でしょう。
人材育成には時間とコストがかかりますが、長期視点でみると「自社ビジネスの理解」と「デジタルリテラシー」の両方を兼ね備えたDX人材は、自社の強みとなります。
おすすめ記事:
「DX人材」についてはこちらもご覧ください:
DX人材とは〜経済産業省が考えるDX人材像から読み解く、求められる人材スキル
社内でDX人材を育成するメリット
企業のDX戦略推進が求められている今、DX人材の不足は深刻な問題になりかねません。自社内でDX人材を育成することは大変ですが、それでも自社にとってのメリットも大きいです。ここからは自社で「DX人材を育成するメリット」について紹介していきます。
事業に最適なDXが推進できる
DX導入に関わる人材は「既存業務の効率化」だけでなく、既存事業の課題や問題点を踏まえた上で「事業の改善案を立てる」ことや「新しい事業の立案」など、自社の経営戦略にも積極的に関わっていくことが重要です。
そのため、外部からDX人材を登用するよりは、既存事業や既存システムを知っている社員のほうが、より自社に最適なDXを推し進めていくことができます。
さらに、自社でDX人材を育成することで、既存システムを活用したDX戦略はもちろん、現場の状況や意見を取り入れたり、既存事業に付加価値を付けたり、あるいは顧客視点で新しいビジネスチャンスを創造するなど、自社社員でしかできないようなDX化を推進することが可能になるでしょう。
DXのノウハウを社内に蓄積できる
DXへの取り組みは「中長期的なアプローチ」で進めることが重要であり、そのためには社会情勢や市場環境やテクノロジーの進歩など、あらゆる変化に対応していくことが求められます。
しかし、個別のプロジェクトごとに外部のDX人材にばかり頼っていると、肝心のDXに関するノウハウやスキルが社内に残らないというデメリットが発生してしまいます。
ノウハウやスキル不足は「DX推進を阻害する要因」の一つにもなるので、DXのノウハウやスキルを社内に残していくことはDX推進のためにも重要です。
もし社内でDX人材を育成することができれば、中長期的にDX戦略を進めていくために必要なノウハウやスキルを「自社内」に蓄積していくことができます。
DXに最適な社内体制が構築できる
企業のDX化を成功させるには、一つの部署だけではなく組織全体で取り組んでいけるかがポイントになります。そのためには部署間のシームレスな連携がとても重要で、あらゆる調整をスムーズに実施していくことが大切です。コンサルタントや外部ベンダーに頼っていると、この組織連携という点で苦労するケースがあります。
社内事情や組織内の問題点を把握している自社の社員であれば、部署間の調整や連携をスムーズに行うことができます。さらに、現場からの意見を反映させやすくなり、あらゆる問題に対してスピーディな対応が可能です。
また、自社の人材であれば「組織変革」や「経営戦略の転換」などの大きな変化にも、迅速に対応することができるでしょう。
一貫性のあるシステムが構築できる
DX化に活用するシステムは、新規に構築したり、改修したりするだけで終わりではありません。定期的にアップデートを繰り返しながら、安定して運用できることが理想です。
継続してシステムに関わることができるDX人材が社内にいると、長期間にわたってシステムを安定運用できます。
また、自社のDX戦略を十分に理解していて、プロジェクトの立案や企画にも関われる自社の社員であれば、自社にとって最適なシステムを構築することができます。
さらに社内にDX人材がいることで、中長期的な視点で一貫性があるシステムを構築することが可能です。そして、一貫性があるシステムが構築できれば、トラブルが起こったとしても対応しやすくなるでしょう。
理想のDX人材を育成するためのステップ
自社でDX人材を育成するには、適切なステップを経ながら育てていくことが大切です。そうすることで、自社にとって理想となるDX人材を効率よく育成することができるでしょう。
ここからは、DX人材育成のステップを解説していきます。
ステップ1|DX人材に必要なスキルを見極める
DX人材として育成していくには、必要な「スキル」や「資質」を備えているか、それを見極める必要があります。デジタル技術やデータ活用に精通していることはもちろん、ビジネススキル、人間性といったことも重要でしょう。なぜなら、組織全体でDXを推進していくには、リーダーシップやコミュニケーション能力が必須になるからです。
また、こういった人材は社内全体から集めることが大切で、特定の部署や階級に限定してしまうと組織全体でのDX化が進めにくくなります。
それぞれ違う立場で、違う意見を持つ社員たちが自社DXの中心的な役割を担うことができれば、組織内のモチベーションも高まるでしょう。さらに、課題解決もスピーディに進められるだけでなく、相乗効果によって新しいビジネスモデルが生まれる可能性もあります。
(1)DX人材が身につけるべきスキル
【デジタルリテラシー】
デジタル情報を適切に理解して、それを活用できるスキルのことです。また「ビッグデータ」とか「ブロックチェーン」といったIT用語の理解も必要ですし、最新技術に関する基本知識も備えておくと良いでしょう。さらに、システムを安全に運用するためのセキュリティに関する知識や技術も求められます。DX戦略では「顧客視点での価値創造」も重要なポイントですから、UI/UXに関する知識も持っておくと良いです。
【ビジネススキル】
DX戦略の推進に求められる人材というのは、DXを通じて自社の商品やサービスの市場価値を高められる人です。ですから、デジタルに詳しい技術者というよりも、デジタルリテラシーをビジネスに応用できるスキルが求められます。もちろん経営視点で物事を判断することも大切ですし、市場環境や社会情勢などにも敏感でなければなりません。さらに、マーケティングに関する知識や経験があると、自社のDX戦略にも役立つでしょう。
【ヒューマンスキル】
企業のDX戦略では社員全体を巻き込んでいけるかがポイントで、そのためにはDX人材の人間性も問われます。コミュニケーション能力を含めた適切な人との関わり方が求められ、社内全体がスムーズに動けるよう潤滑油のような役割ができるのが理想です。デジタルへの知識が乏しい社員に対しても「わかりやすく」伝えるスキル、論理的思考で物事を判断して言語化できるスキルなど、総合的な能力も求められるでしょう。
(2)育成すべきDX人材の職種とチーム組成
ここまで紹介してきたように、DX人材には様々な適性が求められます。さらに企業でDXを推進していくには、それぞれ役割が異なった人たちが「チーム」で取り組むことが重要です。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、DX人材を以下の6つの職種に分けています。
- プロデューサー
- ビジネスデザイナー
- アーキテクト
- データサイエンティスト/AIエンジニア
- UXデザイナー
- エンジニア/プログラマ
これらの職種のうち、DXやデジタルビジネスの実現を主導するリーダーとなるのが「プロデューサー」です。自社でDX人材を育成していく場合、最低でもプロデューサーは育成するようにしましょう。
また、他のDX人材についてはこちらの記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。
DX人材とは〜経済産業省が考えるDX人材像から読み解く、求められる人材スキル
ステップ2|知識やマインドセットを座学で学ぶ
DX人材の適性がある社員を選定できたら、まずはハンズオン講座(体験学習形式)や外部講師による講義で、DXに関する知識やマインドセットを学びます。体験学習を通じてシステム操作をしたり、データを取り扱ってみることで、よりDXがイメージしやすくなり理解も深まるでしょう。
DXはチームで取り組むものなので「リーダーシップ」に関する学びも必要です。外部講師によるリーダーシップ研修などを活用して、リーダーとして育成していきましょう。
また、DXを推進していくにはブレない「マインドセット」も大切なので、実際にDXを成功させた人物を社外講師として招き、経験談や成功体験などを語ってもらうのも効果的です。
ステップ3|OJTで実行力をつける
座学でDXに関する知識やスキル、マインドセットなどを学びつつ、さらに「OJT(On the Job Training)」をしながら実行力を身に付けていきます。座学で学んだことを実務に活かすためにも、このOJTはとても重要なステップです。座学で学びながら、OJTで実践していく、この2つの過程はDX人材の育成には欠かせません。
OJTを実践するときは、いきなり大きなプロジェクトに携わるのではなく、社内の小さなプロジェクトから始めると良いでしょう。必要であれば、OJTをするための小規模プロジェクトを立ち上げても構いません。OJTで実行力が身に付いてきたら、徐々に大きなプロジェクトでDXを実践していくことが望ましいです。
ステップ4|社内外のネットワークを構築する
DX人材の育成は「座学」と「OJT」を繰り返すことを基本としていますが、最新の知見や技術を追いかけるために「社内外のネットワーク」を活用することも大切です。ITやデジタル技術というのは日々すさまじいスピードで発展を続けているため、社内外にネットワークを張って常に最新情報へのアンテナを立てておくと良いでしょう。
たとえば、最新の情報や技術について発信しているコミュニティや、各社の事例などを情報交換しているコミュニティなどに参加して、社外にもネットワークを構築しておくことも大切です。
その他にも、それぞれの分野で第一人者と評価されている人のSNS、ブログ、YouTubeなども欠かさずチェックしておきましょう。
DX人材の育成で覚えておきたい5つのポイント
DX人材を育成していく流れを把握できたら、次は育成する際のポイントについて理解しておきましょう。ここでは具体的な「5つのポイント」について紹介していくので、ぜひDX人材を育成するときの参考にしてください。
社内で学べる環境を設ける
自社内でDX人材を育成するには、選抜された社員にかかる負担を減らし、さらに学びやすい環境を整えることが大切です。まずは、通常業務と並行してDXの勉強ができるよう「社内研修」や「外部講師による社内セミナー」など、業務をしながら社内でDXについて学べるような機会を設けましょう。
また、せっかく社内で学べるような研修やセミナーを開催しても、普段の業務が忙しすぎて参加できなくては本末転倒です。DX人材の育成に選ばれた社員の業務調整というのは、DX推進をする上でも重要な項目になります。選抜された社員が所属する部署の上司や同僚だけに任せるのではなく、経営陣も積極的に関わっていくことでDXに対する本気度を示しましょう。
スモールスタートで成功体験を積み重ねる
自社にDXを導入するとなると、社内全体に影響を及ぼすことになるため、少なからず「反対する社員」や「不満を持つ社員」が出てきます。いきなり大きなプロジェクトを任せると、関係者の協力が得られず失敗してしまう可能性も。そうしたリスクを回避するため、まずは小規模なプロジェクトから任せて、小さくてもいいので成功体験を積み重ねてもらうことがポイントです。
DX人材の育成プランのために小さなプロジェクトを作ってもいいですし、大きなプロジェクトを細かく小単位のプロジェクトに分けても構いません。はじめは成功へのハードルが低い小規模のプロジェクトをいくつか経験してもらい、成功体験を重ねながら徐々に大きなプロジェクトを任せていきましょう。
DX人材育成の過程を全社共有する
DX人材の育成過程については、育成に関係する部署だけでなく「社内全体で共有する」ことが望ましいです。自社でDXを推進する目的やビジョンを示すのはもちろんですが、こういった人材育成の過程も公にすることで、他部署からもサポートしてもらえる環境作りができます。仮に一つの取り組みに失敗したとしても、それを受け入れてくれる寛容さも生まれるでしょう。
さらに、プロジェクトへの取り組み過程、成功体験だけでなく失敗体験なども「可視化」しながら社内共有することで、社内全体のDXに対するモチベーションアップにも繋がります。また、成功や失敗を共有することで新たなアイデアが生まれることもあり、次なるイノベーションへの期待もできるでしょう。
内製化と外部委託の範囲を明確にする
DX人材を育成するにあたっては、どういったスキルを自社内で教育するのかを明確にしておきます。DXに関する全てのスキルについて自社で育成できるのが理想ですが、現実にはかなり難しいです。どのスキルを自社で育て、どのスキルを外部委託するのか、あらかじめ内製化と外部委託の範囲をしっかり決めておきましょう。
とくに中小企業では、育成部門を作ったり、専任の担当者を決めるのは難しいので、はじめは大部分を外部委託するケースが多くなります。そのため、DX人材を中途採用をしたり、外部リソースを活用したりして、プロジェクトを進めながら長期的な視点でDX人材を教育していくと良いでしょう。
なお、大企業では自社内でDX人材の大部分を育成しようという流れがあることも知っておきましょう。
長期視点で全社的なリテラシーアップを図る
DX人材の育成を通じて、会社全体のDXリテラシーを向上させていくのも重要なポイントになります。なぜかと言うと、DX推進者だけでなく「現場スタッフ」へもDXを浸透させていくことで、単なるIT/デジタル化ではなく自社の「経営改革」や「ビジネス変革」が達成できるからです。
また、DXの推進役となる人材だけを育成していても、自社のDX化は進んでいきません。実際にデータやシステムを活用する「営業部門」や「マーケティング部門」や「製造部門」や「カスタマーサポート」などに所属する社員たちにも、長期的な視点でDXリテラシーを根付かせていきましょう。そのためにも、DX人材には忍耐力、実行力、柔軟性なども求められます。
DX人材育成に関する助成金・無料セミナー
DX人材の育成については国の基本方針の1つでもあり、政府や自治体から様々な助成制度を受けることができます。中小企業や小規模事業者でも受けられる助成金や補助金などもあるので、ぜひ自社のDX人材育成に活用してください。
人材開発支援助成金(厚生労働省)
人材開発支援助成金は厚生労働省が毎年募集している助成金で、従業員のスキルアップに投資する企業を支援する制度です。
人材開発支援助成金は7つのコースで構成されており、DX人材育成については以下の4コースがあります。
- 教育訓練休暇等付与コース
- 特別育成訓練コース
- 人への投資促進コース
- 事業展開等リスキリング支援コース
2022年度から新設された「人への投資促進コース」では、デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部について助成を受けられます。
また、オンライン研修(eラーニング)と通信制による訓練も新たに対象化され、サブスクリプション型の定額研修サービスについても助成が受けられるようになりました。