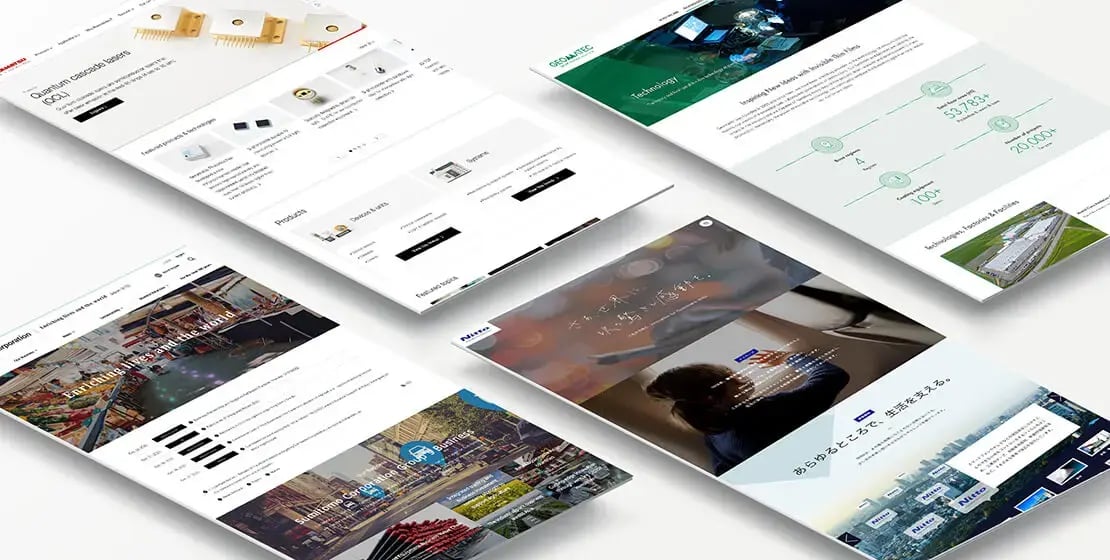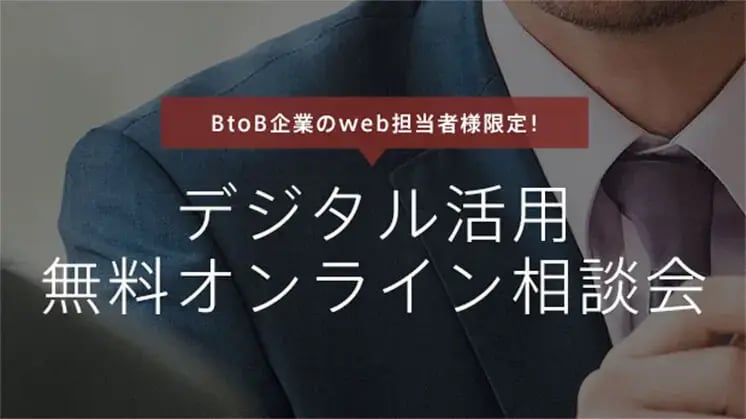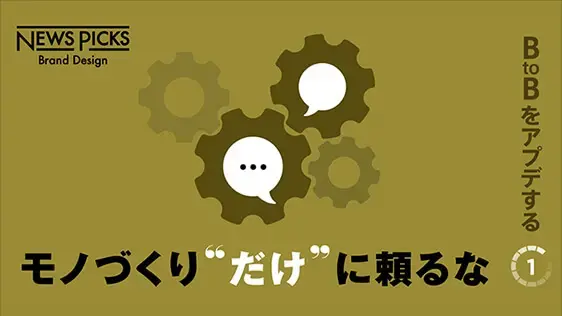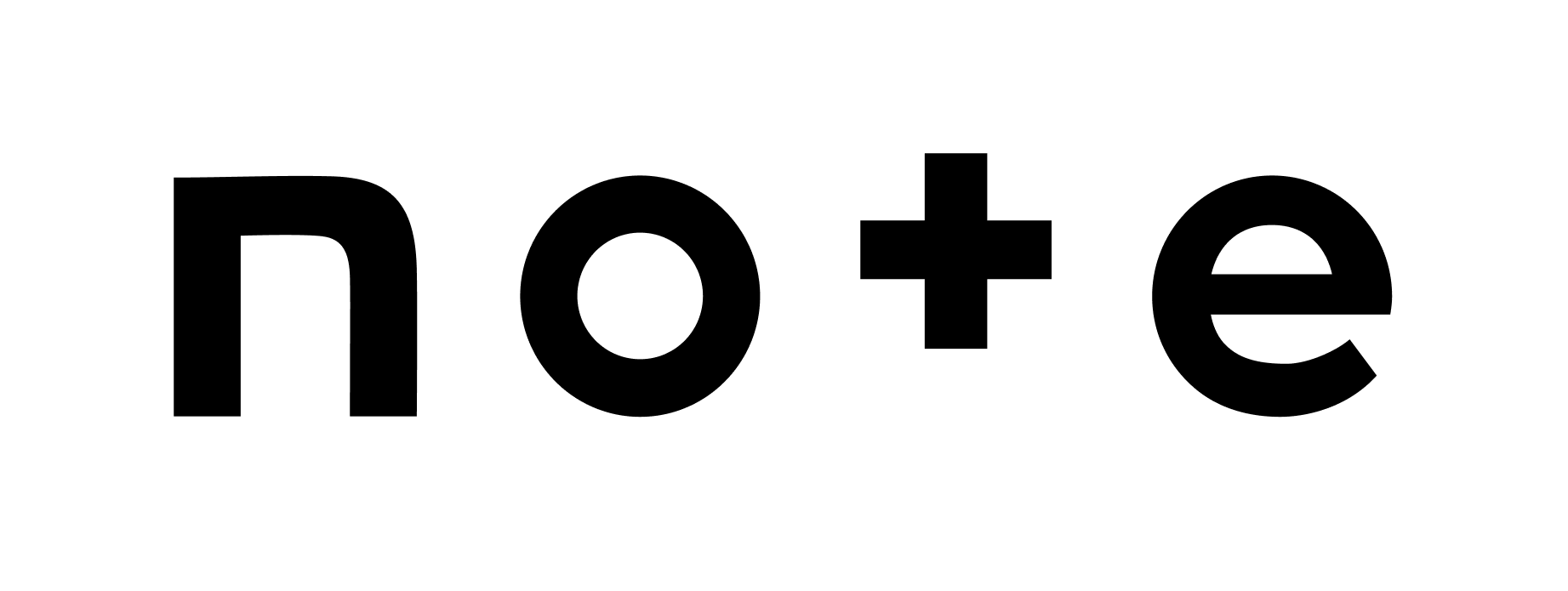制作する全ページを一覧化し、それぞれのURLや、タイトルなどを掲載したリストです。場合により、「新規制作」「移行」「削除」など旧サイトからの変更内容や、meta情報、リダイレクト前のURLなども入れて管理することがあります。
最終的に制作するページに抜け漏れはないか、企業と制作会社の間で最終確認をするために使用します。同時に、URLはWebサイトの構造をGoogleやYahoo!Japanなどの検索クローラーに伝える上で適切なものになっているか、という点も確認が必要です。
8.コンテンツ企画
コンテンツ企画とは、トップページや下層ページに掲載する情報を検討していく工程です。
多くの場合サイトマップの作成と並行して進めていくことになるでしょう。自社が訪問者に伝えたい情報は何か、反対に訪問者が欲している情報は何か、双方の視点から見つめていきます。
自社サービスや商品の情報について、詳細は別途資料で伝えるなどの使い分けも検討しましょう。
9.ワイヤーフレームの作成
ワイヤーフレームとは、Webサイトの各ページについて大まかなレイアウトを作成した図のことです。
ロゴはどこに配置するのか、どの情報を目立たせたいのかなど、ページ内での優先順位に基づいて見た目や配置を仮決定していきます。
制作会社によって、ディレクターが作成する場合もあればデザイナーが作成する場合もあります。INTRIXにはインフォメーションアーキテクトと呼ばれる設計の専門職が複数名在籍しており、彼らがワイヤーフレームの作成を担っています。
10.SEO対策・マーケティング設計
SEOはSearch Engine Optimizationの略称でGoogleやYahoo!などの検索エンジン上で自社サイトが上位に表示されるようにする施策のことをいいます。マーケティング設計は、Webサイトの戦略上の位置づけ、訪問から問い合わせ・資料請求までの流れを組み立てることを指します。
SEO対策とマーケティング設計の双方がうまく噛み合うことで集客効果が高まります。
11.KPI・中間KPIの設計とデータ計測基盤構築
各ページのワイヤーフレームが固まり、マーケティング設計が済んだタイミングでKPI・中間KPIを設計します。特に中間KPIをこのタイミングで定めておくことで、開発時にログが確実に取れるように設定しておくことが可能になります。必要に応じ、Looker StudioやTableauなどを用いたダッシュボード開発も検討します。
取得したい指標が定まったら、Google Tag Managerなどを用いてデータ取得のための設定を進めます。この作業はWebサイトの開発作業と同時期に実施することが通常です。
12.デザインコンセプトの設計
コンテンツ企画では内容を重視しますが、こちらではサイトを利用者が見たときに、どのような印象を抱いてほしいかを重視します。例えば創業100年以上の歴史をもつ老舗和菓子店と創業5年目のIT企業とでは、テイストが大きく異なってくるでしょう。
デザインコンセプトに基づいて、ベースカラーやフォント、必要な写真素材のイメージが決まっていきます。すでにVI(ビジュアルアイデンティティ)ガイドラインにこれらが定められていれば、それを利用します。その他、ロゴやタグラインなどの規定がCI(コーポレートアイデンティティ)ガイドラインにまとまっていれば、それもデザイン時に必要になります。
CIやVIガイドラインは、デザインコンセプトを定める上で重要な前提条件になりますので、あらかじめ整理して、制作会社に渡しておく必要があります。
13.デザインカンプ作成
デザインカンプとは、実際に公開されるWebサイトの完成見本のことです。Webエンジニアはデザインカンプに基づいてWebサイトを実装していきます。この段階で大幅な修正を行うと、工数の出戻りが発生しコスト増を招きます。
デザインコンセプト設計の段階で、参考にしたいサイトを共有するなど、慎重な擦り合せをおすすめします。
14.Webサイトの開発・修正
デザインカンプに基づいてWebサイトを実際に作っていきます。コンテンツ企画で考えたテキストは遅くともこの段階までに用意しておきましょう。写真・テキスト素材ともデザインカンプ作成前に揃っている状態が理想です。
ページ数が数百、数千にのぼるような大規模開発では、何段階かに分けて確認・修正を入れるほうがプロジェクト関係者の負荷も少なく効率的です。イントリックスでは、規模によって2~4回程度に分けて進行することが平均的です。
15.Webサイトリリース
完成したWebサイトをインターネット上に公開します。修正を重ねていても、開発環境では動作していたものが本番環境では動作しない、という現象が起こる場合があります。また、公開後に誤字脱字を発見したりリンク切れが発覚したりすることもあります。
そのため、公開までのスケジュールにはある程度余裕を持っておく必要があります。万が一の事態に備え、リリース前には2週間から1か月の凍結期間を持ち、これを事実上のバグ対応のバッファとすることがほとんどです。
また、発注時には、公開後の保守対応(1〜2ヶ月程度)も含めて依頼することがおすすめです。