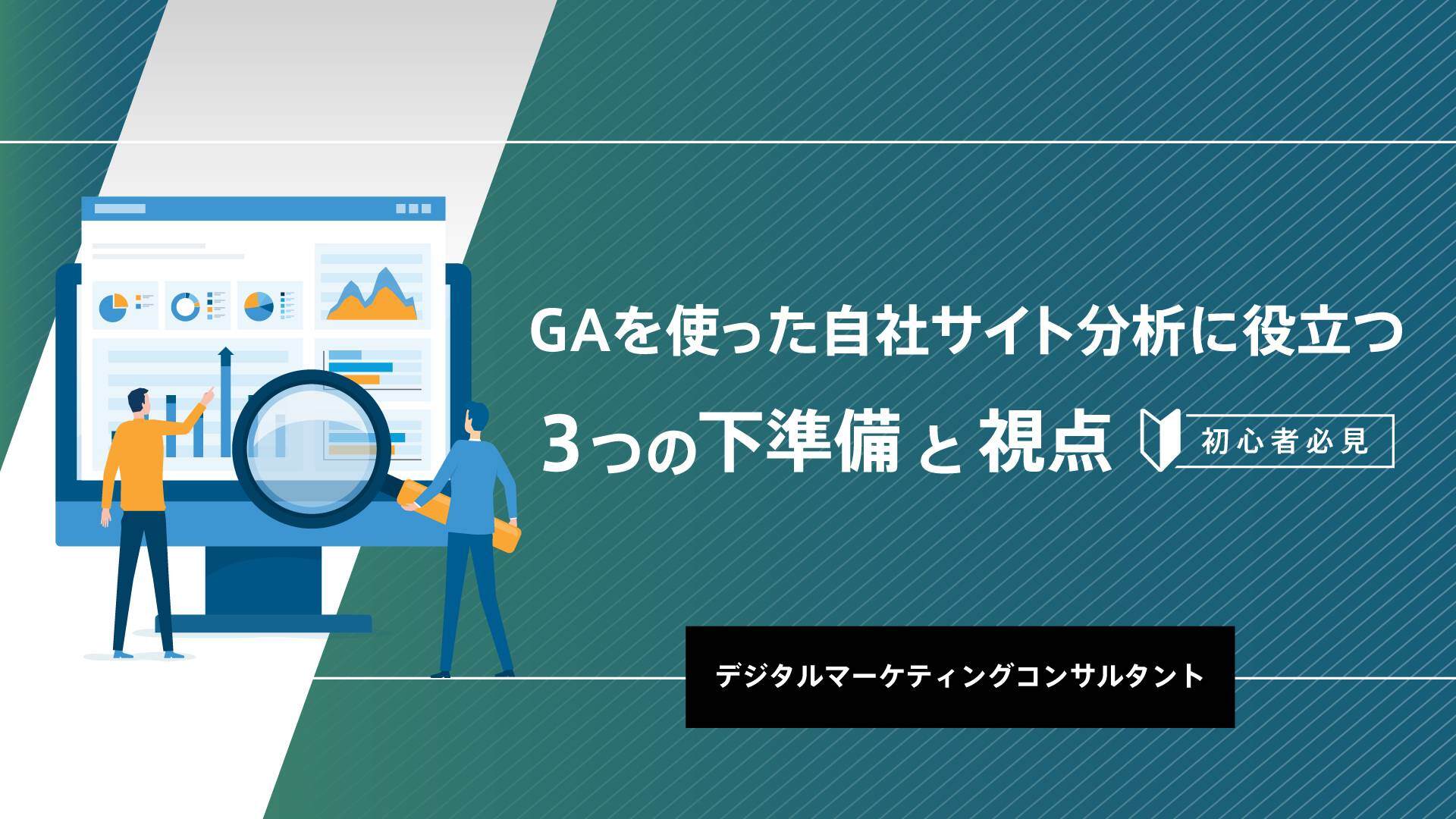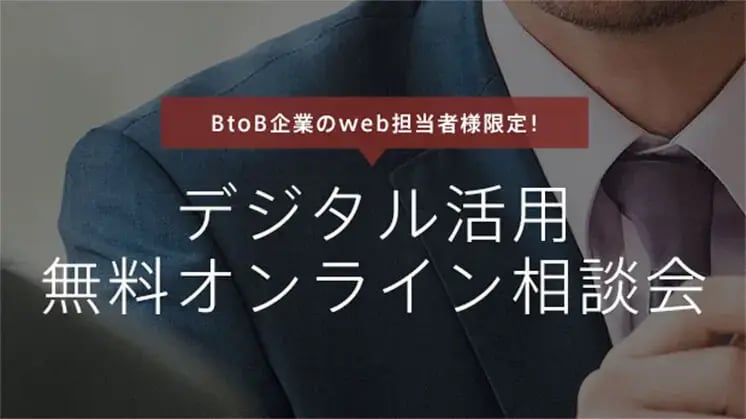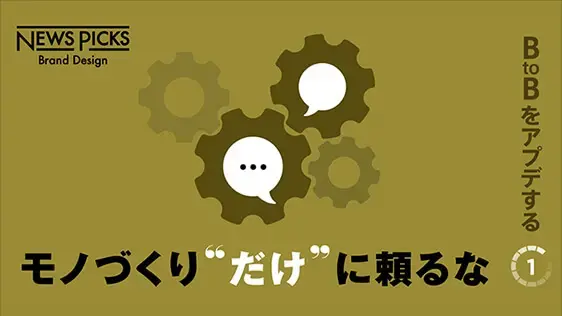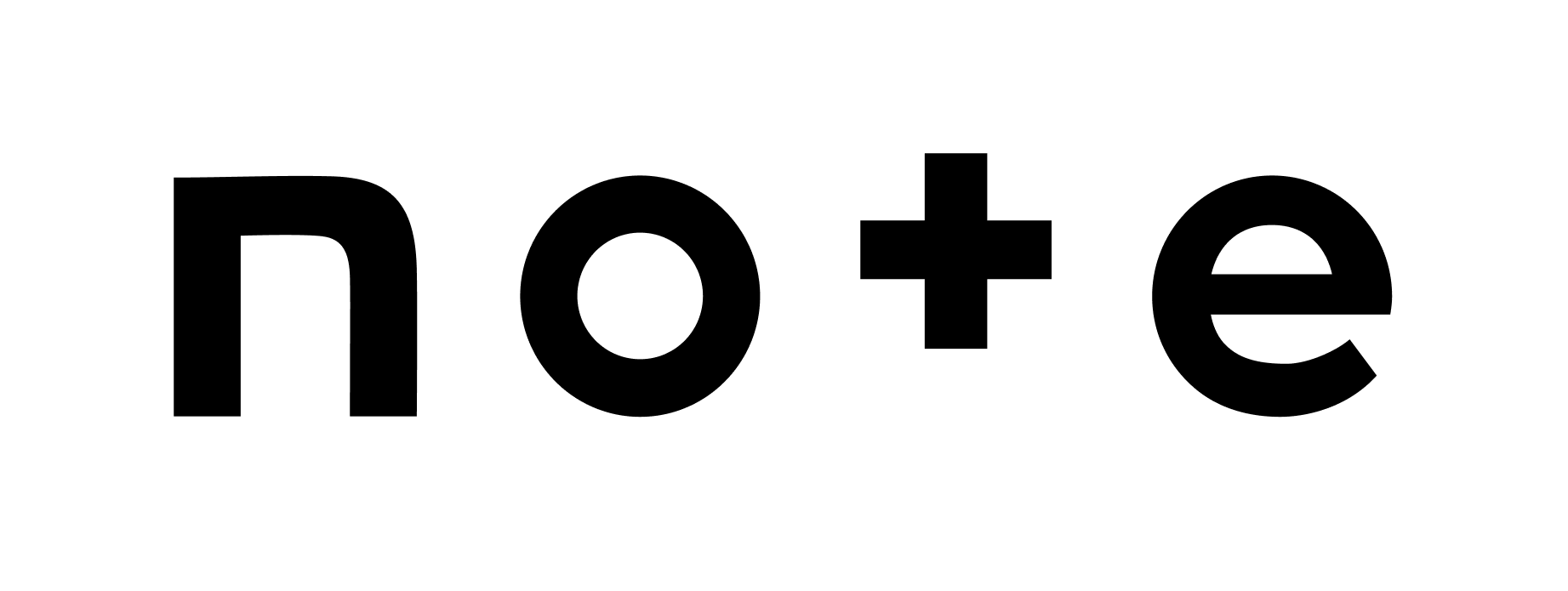分析の下準備―課題が潜んでいそうなポイントの予想を立てる
サイト分析を成功に導くには、まずその前段階として、現状どのような課題が潜んでいるかを予測することが重要となります。GA4ではさまざまなデータを確認できますが、仮説を持たないまま数値を一つずつ見ても、散発的な気づきは得られるかもしれませんが、サイト改善の本質に迫ることはできません。
それでは、課題を特定するためにはどうすればよいのでしょうか。筆者がよく用いるアプローチは以下の3つです。
1.サイトの重要ユーザーと目的を振り返る
基本的なステップではありますが、まずはサイトの運営目的と重要ユーザーを振り返りましょう。
重要ユーザーは、どの業界や職種に属しているのか、どのような課題を抱えているのか、どのような経路を通じてサイトに到達するのか、そしてサイトで求める情報は何か、などを細かく洗い出します。
過去に作成したペルソナやサイトの訪問データなどのリソースがあれば、それらを今一度丁寧に確認することをおすすめします。こうした資料を改めて見直すことで、現状のサイトで改善が求められる部分や、ユーザーニーズに合ったコンテンツ施策はどのようなものかなどの大まかな検討がつくはずです。
一方で、これまでユーザーについての理解が十分でなかった場合は、この機会にペルソナの構築から着手し、そこから分析の方向性を定めていく必要があります。ユーザーに対する深い理解がなければ、適切な分析は行えません。
併せて、サイトの運営目的を再確認します。目的に応じて、サイト改善に向けて注目すべきポイントは異なってくるためです。
例えばリード獲得サイトでは、問い合わせやメルマガ登録などのコンバージョン数を重視し、認知度向上を目的とするコーポレートサイトでは、指名検索数が重要な評価指標になります。
2.自分が使いづらい、探しにくいと思う箇所を考える
自身でサイトを実際に使い、使いづらさや違和感を感じる個所を洗い出しましょう。ナビゲーションの分かりづらさ、コンテンツへのアクセスのしづらさ、全体的なユーザビリティの課題など、円滑なユーザー体験を阻害する問題点をリストアップすることで、サイトの抱える課題が見えてきます。
筆者がこれまでご支援してきたプロジェクトを振り返ると、以下のような課題が多くみられました。
- グローバルメニューの数が多いことによるナビゲーションの複雑さ
- 専門用語の過剰な使用による内容理解の難しさ
- 行間が狭く、文章が詰まっていることによる読みにくさ
- 文字サイズが小さいことによる視認性の低さ
- 古い製品情報や欠如した検索機能による情報不足
また、かつては最新だったサイト構成や機能が、時間の経過とともに陳腐化しているケースも少なくありません。
一方で、自社サイトを日常的に利用する担当者は、使いづらさを見つけるのが難しい傾向にあります。そのような場合は、他部門のメンバーに協力を求めると効果的です。サイトを普段使わない者の新鮮な目線から、明確な問題点を指摘してもらえる可能性が高まります。
もちろん、分析を通じて課題を見つけ、その課題を深く掘り下げるためにサイトを確認するアプローチも有効です。
3.関係者へのヒアリング
サイトリニューアルやコンテンツ制作に携わった関係者へのヒアリングは、データだけでは見えにくい課題や改善の方向性を明らかにするための重要な手段です。特に、プロジェクト全体を俯瞰できる立場の関係者からは、過去の取り組みとその成果に関する幅広い示唆を引き出せるでしょう。
筆者が分析を担当したオウンドメディアでは、複数のカテゴリにわたってコンテンツを展開していましたが、分析対象が広範囲に及ぶため、重要課題の特定が困難でした。そこで過去の担当者へヒアリングしたところ、特定のカテゴリに注力していたことが判明し、優先的に分析すべき領域が明確になった経験があります。
このように過去の担当者へのヒアリングによって、課題の示唆を得られるだけでなく、分析の焦点をより明確に定められ、重要度の低い部分への無駄な注力を避けられます。
ヒアリングを行う際のポイントは、明確な目的意識とゴールを持つこと、そして現状の問題点を事前に共有し、具体的で建設的なフィードバックを求めることです。例えば「特定コンテンツがターゲットに届いていない」「回遊に課題がある」「ページ速度が遅い」などWeb分析の観点で具体的な課題や気になるポイントを提示することで、今のサイトをより良くするための議論につながると考えます。
サイトデータから仮説を立ててからヒアリングに臨めば、定量データと関係者の定性的な経験を掛け合わせられます。これにより分析の解像度が向上し、より有益な示唆を得られるでしょう。