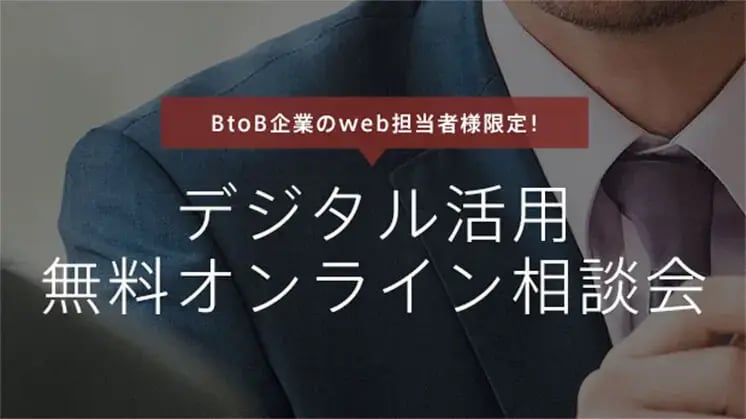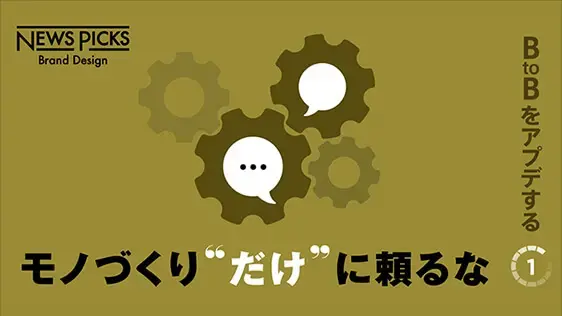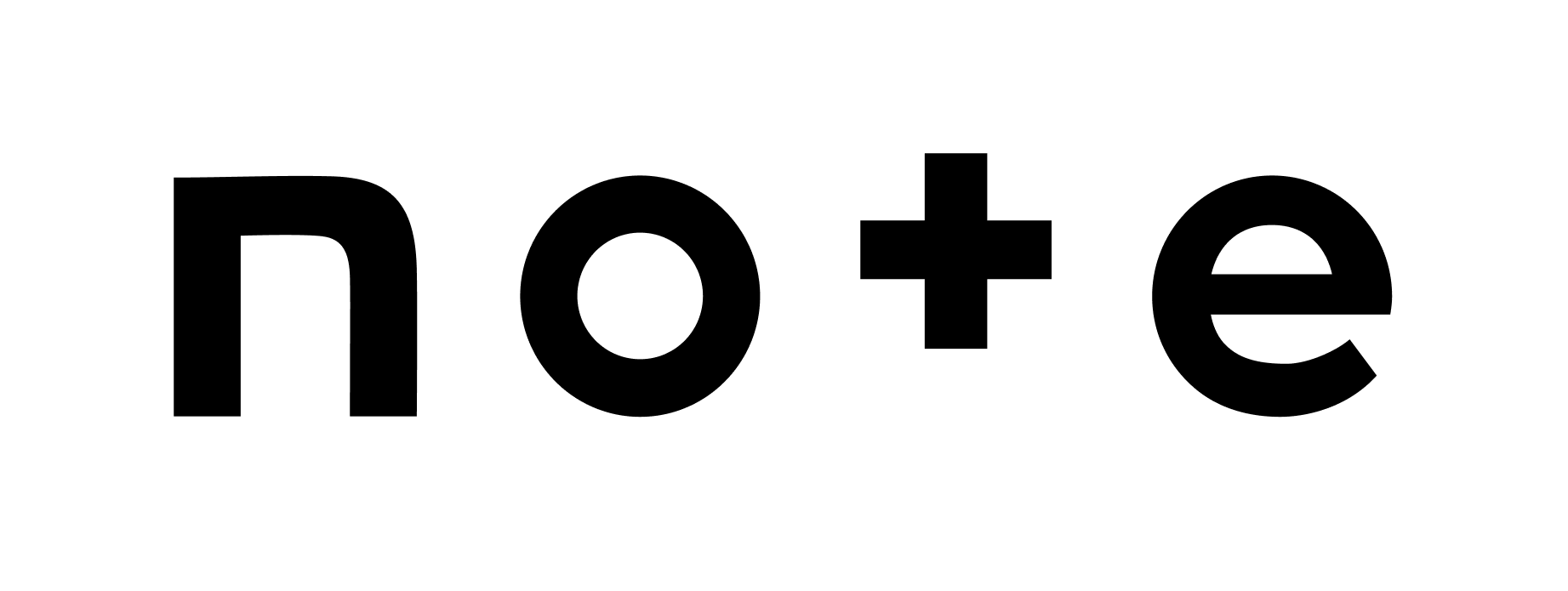3. デバイスの多様化:スマホ・タブレットでも快適に閲覧できますか?
自社のWebサイトは、PCとスマートフォン、タブレットなど、それぞれのデバイスに適した設計・デザインになっているでしょうか?
一部のページのみがモバイル表示に対応していたり、PCサイトとモバイルサイトで情報量に差があったりしていませんか?
Webサイトの閲覧環境や端末は、今や多種多様となっています。
現在のGoogle検索では、2018年にモバイルファーストインデックス(MFI)が導入され、検索順位の決定においてモバイル版のコンテンツを優先的に評価・インデックス化しています。つまり、モバイル端末への対応が遅れているということは、検索順位が下がる可能性があり、その結果、届けたいユーザーに情報を届けることができていない可能性が高いということでもあります。
操作性の面でも、問題が起きることがあります。
たとえば、PC画面を前提に作られたWebサイトをモバイルデバイスで見ると、以下のようなトラブルが起きやすくなります。
- 横スクロールが発生し、操作しづらくなる
- 文字や画像が小さくて見にくい
- ボタンやリンクが小さすぎる、間隔が狭くタップしにくい
こうした問題は、ユーザーにとって使いにくいと感じさせてしまい、結果的にページから離れてしまう大きな要因となってしまいます。
現在では、Googleが推奨する「レスポンシブデザイン」を採用することが一般的です。レスポンシブデザインとは、1つのソースコードでブラウザ幅にあわせてレイアウトを最適化する手法のことで、PCサイトとモバイルサイト別々にファイルを用意する必要がなく、同一のコンテンツとして管理することができるため、メンテナンス性が向上します。
このようにそれぞれのデバイスに適した設計・デザインを行うことで、ユーザーには「使いやすさ」を提供でき、企業側にとっても運用の効率化が期待できます。双方にとってメリットの大きい取り組みと言えるでしょう。