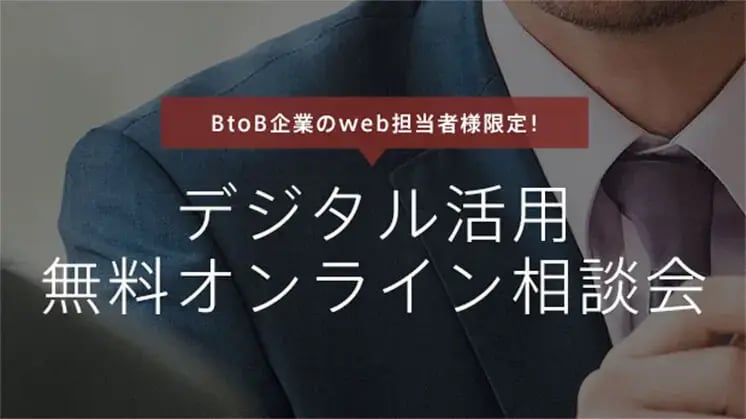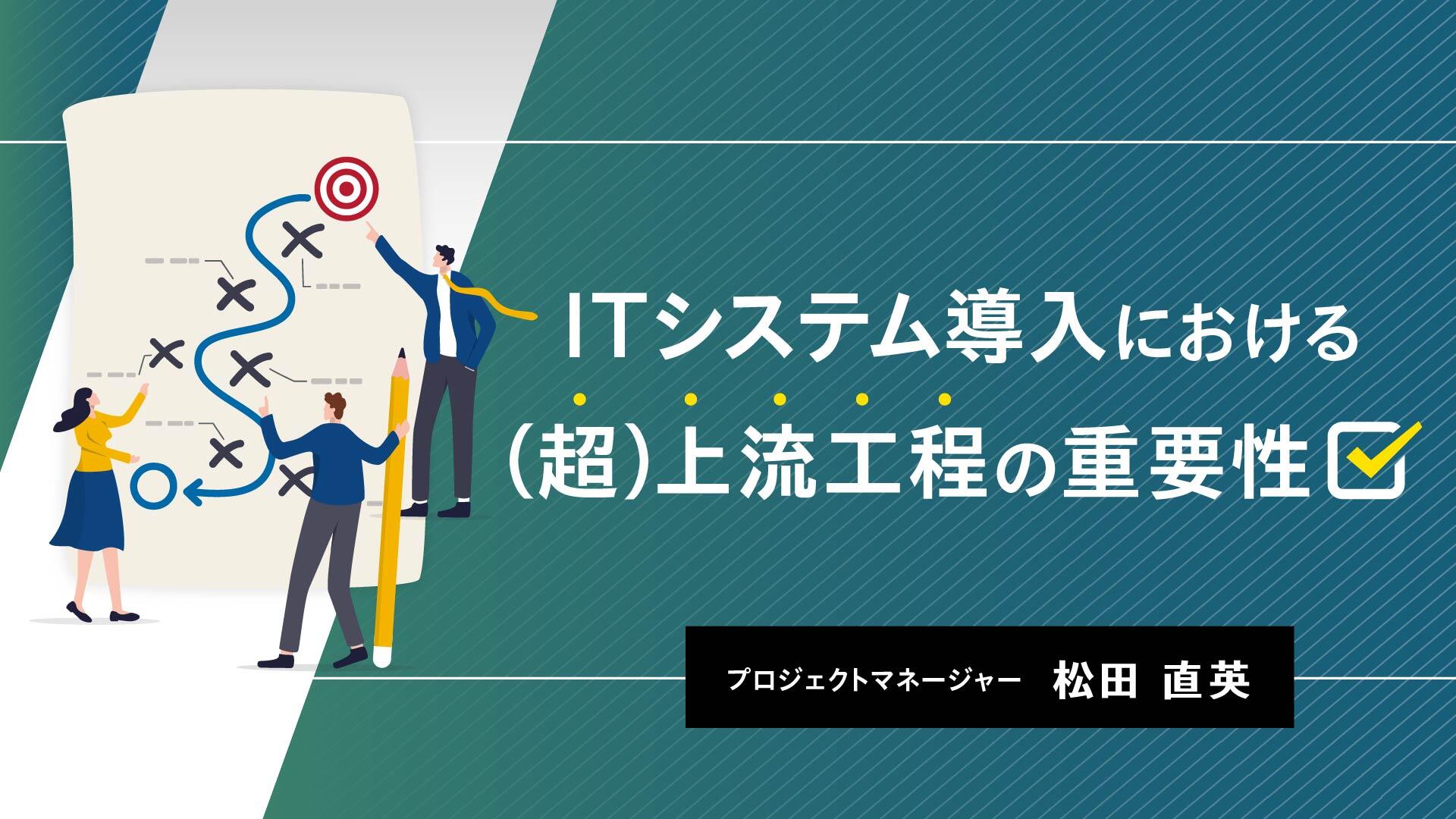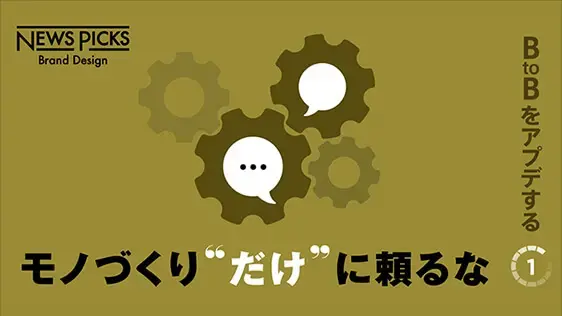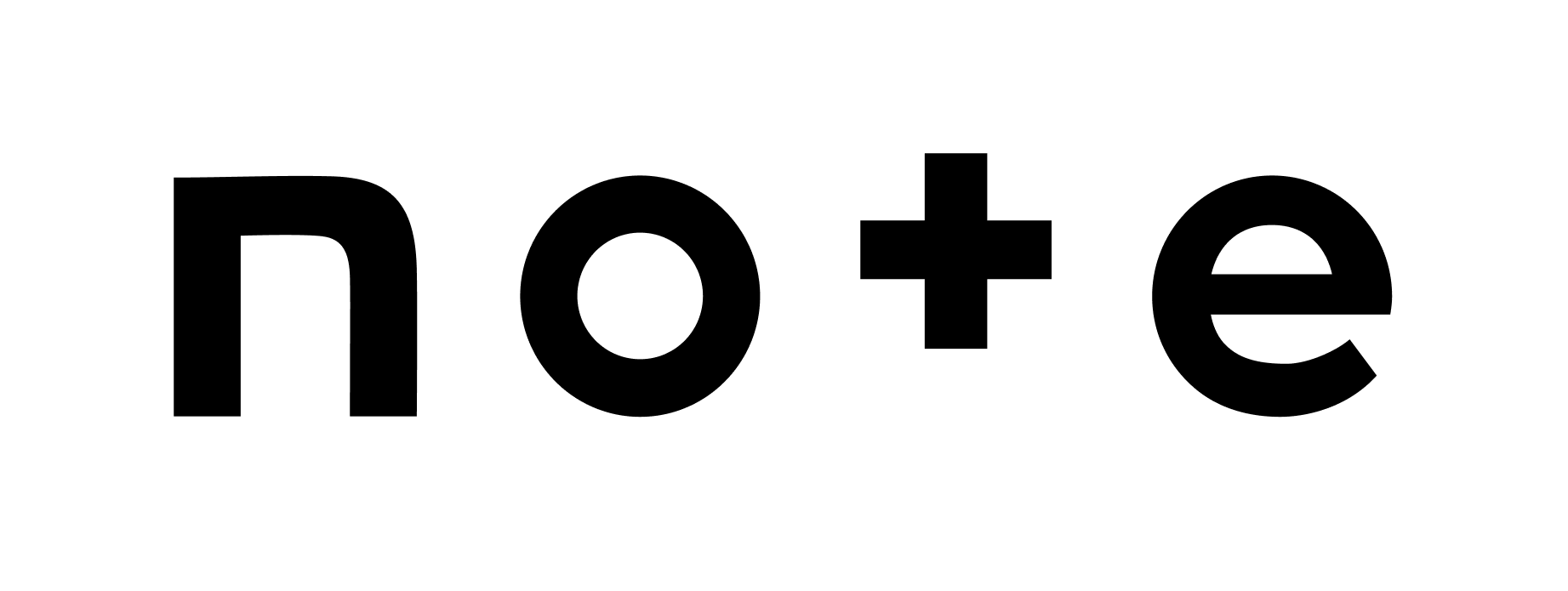(3)顧客企業の公開文書を参照し重要キーワードを抽出
企業のコーポレートサイトで公開されている「中期経営計画書」や「有価証券報告書」などから「経営戦略/IT戦略」にあたる重要キーワードを抽出し、今回のITシステムの位置づけを仮説構築します。
(4)一次効果・副次効果を共有
近視眼的にならないよう、ステークホルダーとは効果についても認識共有します。一次効果は「短期視点のITシステム導入による機能面の一般的な効果」。副次効果は「(2)(3)と照らし合わせ、関連づけた仮説効果」。定量効果だけでなく定性効果も視野に入れて整理しましょう。
(5)対象者別にベネフィット(想定/期待効果)を整理
ITシステムを導入することでの、主管部署、ならびに関連部署(グループ全体、子会社)などが得られるベネフィットを、(2)、(3)、(4)を踏まえて、"想定効果"を整理します。これによって、ステークホルダーはより腹落ち感が高まります。
(6)プロセス成熟度/能力レベルの認識合わせ
「COBIT5」という企業や組織のITガバナンス成熟度を測るフレームワークがあります。これを使ってシステム導入対象としている組織や部門の現在の「成熟度/能力レベル」の確認(As-Is)を行い、中長期等で目指す成熟度設定(To-Be)を行い、その実現を目指すための想定計画/施策を示します。
(7)中期での展開を提案
ITシステム導入後の、将来フェーズのシナリオも合わせて提案します。(4)~(6)を実現するための「仮計画」を示し、例えば「全体最適化」や「横展開/適用領域拡大」などを示し、ステークホルダーの納得感を向上させます。
以上が、「(超)上流工程」を重視した提案書作成のひとつのアプローチになります。もう少しイメージしやすいように、次は具体的な事例をもとに解説していきます。