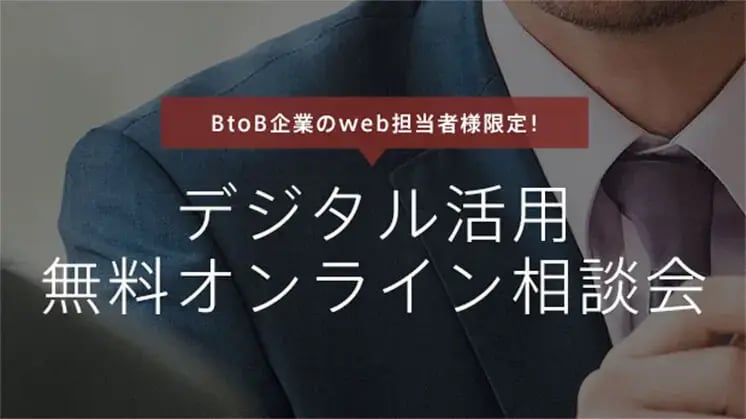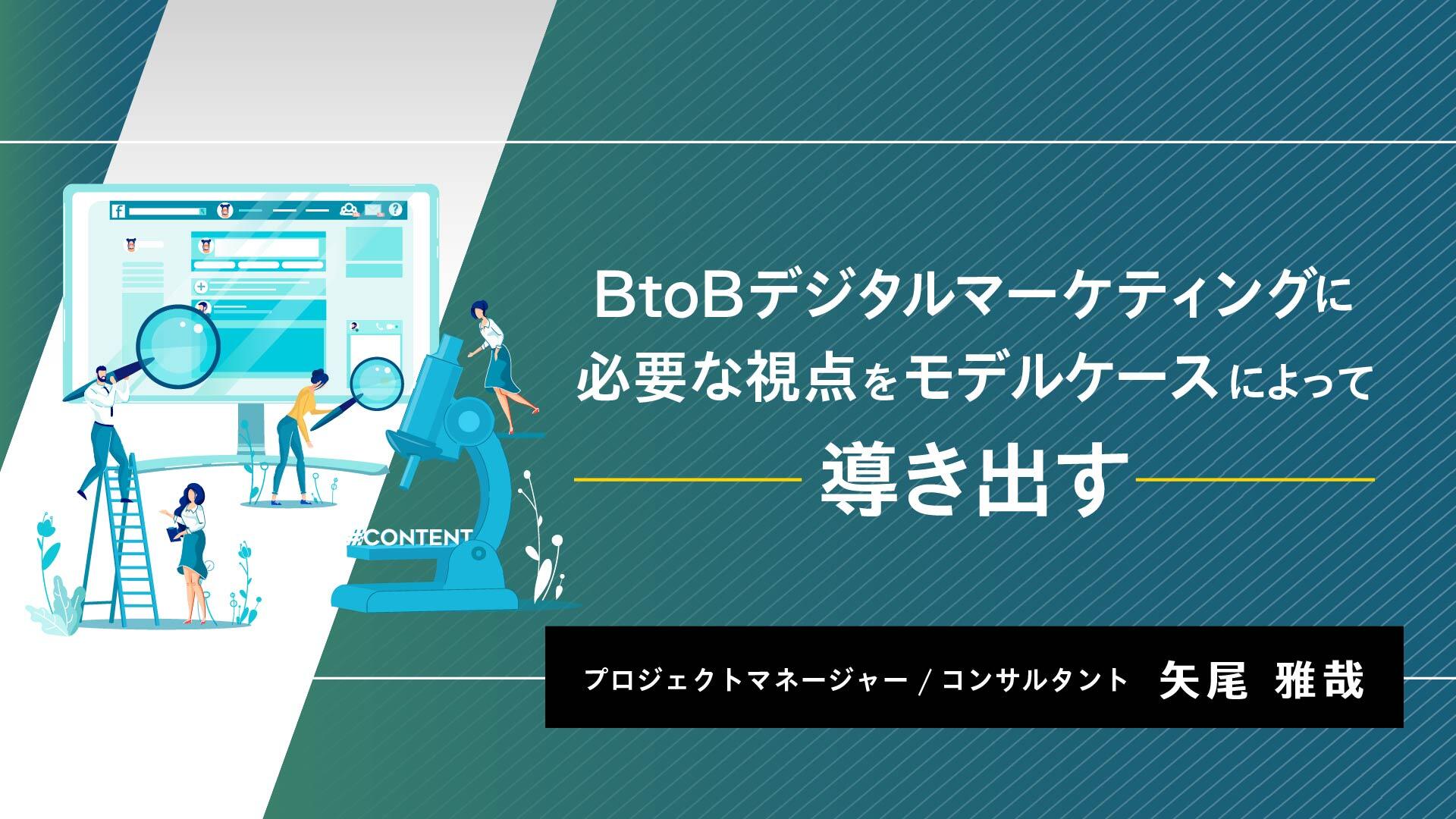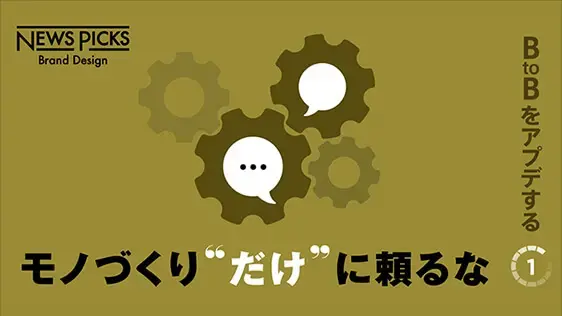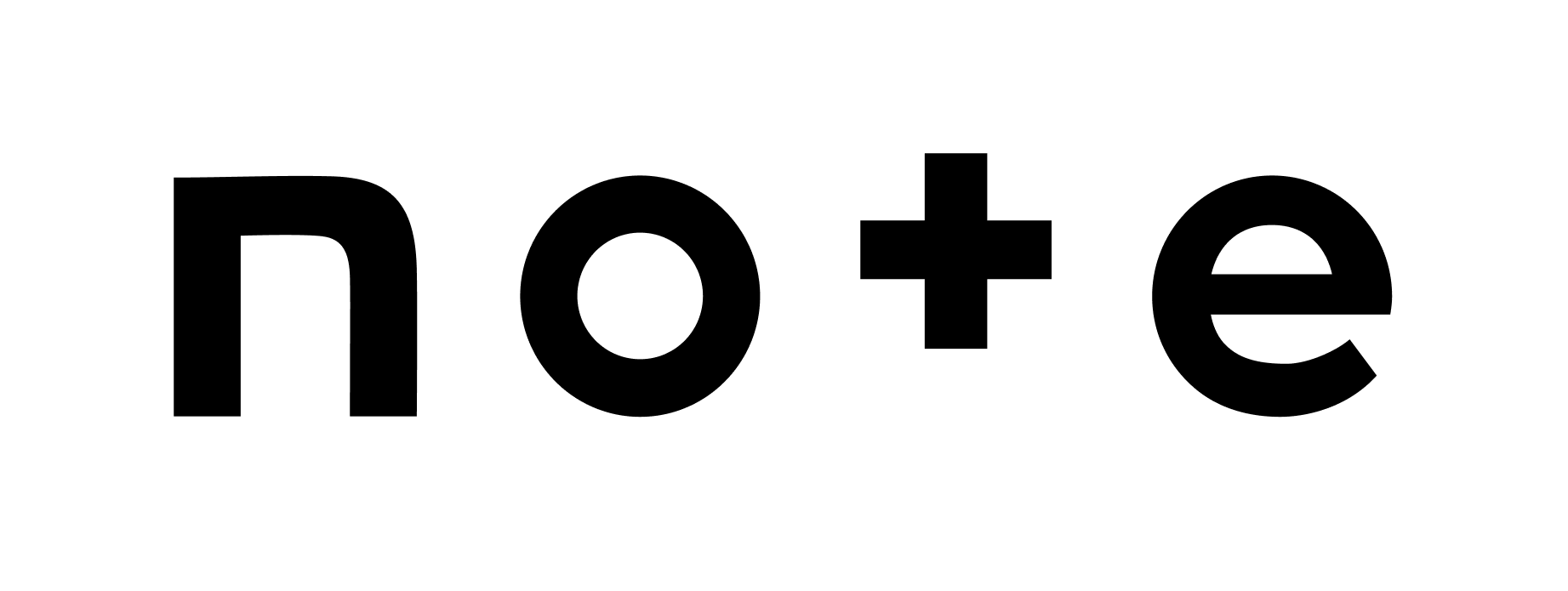それぞれの解決策を見ていきましょう。
①の解決策
指名検索数を増やすためには、自社の認知度を高めることが不可欠です。「○○といえばA社」と高い第一想起率を持たれれば、顧客が商材を比較検討する際に、指名検索によって自社ブランドを選んでもらえるようになります。
自社の第一想起率を高めるためには、情報感度が高まっている興味関心段階で、自社の存在を認識してもらうことが有効です。
ただし、第一想起されても、商材が優れていなければ最終的に選ばれることはありません。このモデルケースではすでに業界内で一定のシェアを確保しているため、商材の質は十分に高いと考えられます。
したがって、認知さえしてもらえれば最終的に選ばれる可能性が高まります。今後は、潜在顧客層にアプローチすることが効果的であり、そのためには②と③の原因に対処することが重要となります。
②と③の解決策
ニッチ商材はその特性上、関連するキーワードの検索ボリュームが少ないため、SEO施策の効果が限定的です。また、商品名が一般的に流通している商品(家電製品やカメラなど)と同じ場合、ECサイトなどが上位表示されるため、自社サイトをトップ表示させることは困難でしょう。
このような状況に対処するためには、まず上位獲得の難易度が低いキーワードの組み合わせを見つけることが重要です。地道な活動になりますが、Google AnalyticsやSearch Consoleなどの解析ツールを用いて、自社サイトへの流入が発生している検索語句を確認しましょう。
弊社がご支援する際、顧客のみならず、営業部や事業部、研究開発などの関連部門へのヒアリング調査を実施し、顧客が抱える課題や検索時に使用しそうな言葉を把握し、ニッチキーワードやロングテールなキーワードを特定しています。